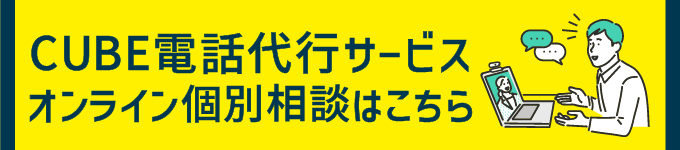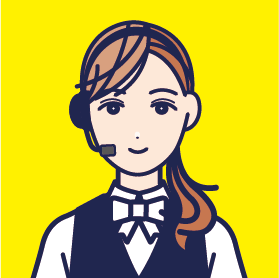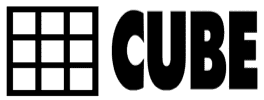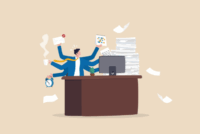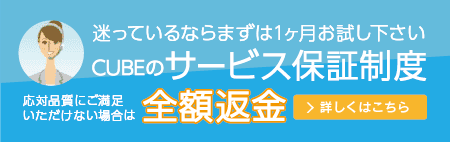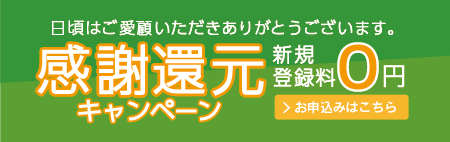難関の国家資格である税理士資格を取得した方は、独立開業を目指す人もおおいのではないでしょうか。
国税庁のHPを確認すると、令和7年3月末日現在の税理士登録者数の67.8%が開業税理士であり、実際に半分以上の税理士の方が独立をしていることがわかります。
本記事では、これから開業を目指す税理士の方に向けて、開業時に抑えるべき電話対応の基本とコツをご紹介していきます。

引用元:日本税理士会連合会
【目次】
なぜ電話対応が税理士の開業初期に重要なのか

なぜ電話対応が税理士の開業初期に重要なのでしょうか。税理士に電話対応は関係ないのでは?と思う方もいらっしゃると思います。
税理士の開業初期の電話対応の重要性について、下記3つのポイントにまとめて解説いたします。
・新規顧客の獲得機会を逃さない
・最初の印象を決めるチャネル
・広告宣伝効果を無くす可能性がある
新規顧客の獲得機会を逃さない
税理士事務所だけでなく、士業全般で新規顧客からの問い合わせは、電話であることが多いです。
税理士の場合は、確定申告や税務調査、法人設立など、顧客にとって大変重要な事柄に関する相談や依頼であるためです。
今後アポを取って本格的に相談をするとしても、まずはどのような対応を行う税理士事務所であるのかを少しでも知りたい、と思って新規顧客は電話をかけます。
そのようなときに、税理士事務所の代表電話が、留守電、もしくはコールが鳴りっぱなしであればどうでしょうか。
紹介を受けている顧客でない限り、他の税理士事務所へ電話をかける人が大多数です。つまり、電話対応が行えない数だけ、新規顧客獲得の機会を失っているということです。新規顧客獲得の機会を逃さないためには、電話対応は重要だと言えるでしょう。
開設後すぐであれば、新規の問合せ数自体は、年20件程度、1カ月ではたった1~2件かもしれません。
しかし、電話問合せはHP問合せよりも圧倒的に成約率が高く2~3割程度が見込めます。電話は少ないからと軽視するのは大きな機会損失ではないでしょうか。
最初の印象を決めるチャネル
事務所の電話に出さえすれば良い、ということでもありません。
新規顧客に対する電話対応は、税理士事務所の印象を決定づけるものと言えます。
新規顧客にとっては、どのような仕事ぶりを見せてくれるのかという期待以前に、「どんな事務所なのだろう?」と考えて問合せされます。
そして耳から入る情報(言葉遣いや話し方、雰囲気)で事務所の印象をジャッジします。
顧客は、時間を割いて問合せをするわけですから、このようなタイミングで暗い声であったり、語尾が強い話し方であったり、早口すぎたりすれば印象は悪くなります。
逆に電話対応で第一印象を良くできれば、その後長く付き合っていく顧問先になり得るかもしれません。
広告宣伝効果を無くす可能性がある
開業後に行うことの1つに、税理士事務所の宣伝活動があります。紹介だけで税理士事務所を継続させていくことは大変に困難だからです。
HP制作に力を入れたり、ポータルサイトに登録したり、SNSで集客したり、WEB広告を利用するなど宣伝方法は様々ですが、どんな方法であっても最初は顧客からの電話での問い合わせがほとんどです。
ということは、せっかくお金や時間をかけた活動であっても、電話対応の品質が悪ければ、顧客は別の税理士事務所へ依頼をしてしまう可能性が高まります。
電話対応の重要性を知っている税理士事務所では、電話対応はコミュニケーション能力が高いスタッフに行わせることが多いと言われています。
税理士が押さえるべき電話対応の基本マナー

税理士事務所の電話対応の重要性を理解した上で、税理士自身が電話対応の基本マナー習得しておくと、税理士事務所の電話応対の品質がぐんと向上します。
本項目では、5つの基本マナーについてご紹介します。
・明るく、聞き取りやすい声で名乗る
・相手の名前や連絡先を復唱・確認する
・用件をしっかりと聞く
・折り返し連絡は“いつ・誰が”を明確に伝える
・正確にメモを取る
明るく、聞き取りやすい声で名乗る
受話器を取って、明るく、聞き取りやすい声のトーンや速さで事務所名を名乗ることで、電話相手に好印象を与えることができます。
また、その好印象は基本的には継続すると言われています。これを初頭効果と言い、最初に提示された情報がその後の印象や判断基準に強く影響する心理効果です。
逆に、名乗りの挨拶で良くない印象を与えた場合、印象を覆すには2時間はかかると心理学の一説で言われています。新規顧客と電話で2時間話すことはほぼ不可能なため、名乗りの挨拶で与えた印象を覆すことは難しいと言えます。
相手の名前や連絡先を復唱・確認する
電話相手の名前や連絡先を聞き間違えたまま通話を続けることはマナー違反なだけではなく、以後、連絡が取れなくなってしまう可能性が出てきます。
特に電話番号の聞き間違いは連絡が取れなくなる可能性が高いため、折り返しの電話が必要な場合は、必ず復唱確認をするようにしましょう。
名前の聞き間違いの場合であっても、企業や自宅宛の折り返しであれば「そんな名前の人はいません」と、間違い電話扱いされてしまう可能性もあります。
復唱確認を行えば、万が一聞き間違いをしていたとしても、「いえ、違います」とその場で訂正をしてもらえます。
用件をしっかりと聞く
相手の用件をしっかり聞くことで、ニーズがつかめて最適な提案を行うことができます。
例えば、よく話を聞いてみたら、当初の話とは別のところに困りごとの原因があったため、依頼内容を変更して提案することで新規顧客から大きな信頼を得ることができた、という事例もあります。
相手がまとまりのない話をしたり、話題が脱線してなかなか戻らなかったりするようなことがあれば、合間にこちらが要点をまとめて確認を取ることも良いでしょう。
ただし、相手が発言している途中で話を遮ってしまうと、相手は不快感や不信感を抱きやすいため注意が必要です。
折り返し連絡は“いつ・誰が”を明確に伝える
折返しの電話が必要な場合は、「いつ」「誰が」電話をするのかをハッキリと相手に伝える必要があります。この2点を伝えないことにより、トラブルになる可能性があります。
特に折り返しの時間について明言していない場合は、「こんな時間に電話をかけてくるなんて思っていなかった」や、「すぐに電話をくれると思ったのに」などの不満が発生しやすいと言えます。
もし予定が未定の場合は、遅くともいつごろまでには連絡できるかを伝えるようにしましょう。
正確にメモを取る
勧誘電話などではない限り、通話中に相手の名前や連絡先、用件は正確にメモを取ることが必要です。
なぜなら、電話で通話中は相手の名前や用件、アポの日時などを覚えていたとしても、電話を切った後は長く記憶に留めておけない人がほとんどだからです。
たとえしばらくは覚えていられても、他の業務などを行っている間に電話の記憶は薄れます。そしてまた別の電話が入ったら、誰からどのような電話があったのかを全て覚えて置くことは不可能と言えるでしょう。
せっかくアポをとっても、その日時を正確に覚えていなければ契約が出来ないどころか、クレームが入ってしまいます。
開業時にありがちな電話対応のリスク

電話対応の基本マナーの次には、開業時にありがちな電話対応のリスクを2つ、ご紹介します。
・電話対応が遅れることによる機会損失
・業務中断による集中力・生産性の低下
対応が遅れることによる機会損失
事務員を雇うと決めている税理士の方でも、開業後すぐは1人で全てを行う場合がほとんどです。
そのため、外出時でも電話対応が行えるように、事務所の代表電話を携帯電話へ転送している、もしくは携帯番号を公開している税理士の方もいます。
しかし、出先では受電が遅れる、もしくは移動中で受電ができないリスクがあります。
また、携帯電話へ転送をかけていない場合は、事務所の留守番電話メッセージを聞いた時点ですでに相手の営業時間外のタイミングや、相手が折り返しを希望した時間を過ぎているということもあります。
一生懸命やっていても、電話対応が遅れてしまうだけで「対応が遅いから他の事務所に依頼しました」なんて言われてしまうリスクがあります。
業務中断による集中力・生産性の低下
開業直後は、宣伝活動や人脈づくりのための活動、顧問契約書や報酬規定の作成、税理士賠償保険の加入などの細々した業務が山ほどあります。
その中で電話対応も行うわけですが、電話が鳴ると今やっている業務を強制的に中断しなければなりません。
集中したい業務中にかかってきた電話が勧誘電話だった、なんていうこともあります。このようなことが何度も続くと、集中力はもちろん、生産性が低下してしまいます。
電話対応は新規顧客獲得の機会だとわかっていても、目の前の業務に集中したい業務があればあるほど、生産性が低下してしまうリスクがあります。
一人税理士でも実践できる電話対応の工夫

一人税理士は電話対応のリスクが大きいのでは?と心配になるかもしれませんが、大丈夫です。一人税理士でも実践できる電話対応の工夫を3つお伝えします。
・私用携帯を利用しない
・定型対応をマニュアル化しておく
・予約フォームやFAQの導入で“電話を受けすぎない仕組み”をつくる
私用携帯を利用しない
私用携帯番号を公開する、私用携帯を連絡手段の主として利用するという税理士の方もいますが、出先でも連絡が取れるというメリットがある反面、いつでも連絡がとれてしまうというデメリットもあります。
営業時間外であっても、休日であっても私用携帯に電話がかかってきてしまうことになれば、電話に縛られた生活になってしまう可能性があります。
オンとオフを分けて生産性を向上させるためにも、私用の携帯番号よりも事務所の固定電話番号を公表する方がおすすめです。
定型対応をマニュアル化しておく
定型対応をマニュアル化しておくと、ある程度の電話対応はマニュアル通りに進めればいいため、効率よく対応することができます。
よく聞かれるとすれば、料金体系、得意分野やサービス内容、事務所までの行き方、相談予約の方法あたりです。
電話対応の基本マナーについても、不安がある方はマニュアル化しておくと良いでしょう。
例えば、
①電話が鳴ったら2~3コール以内に受電する②事務所名を明るくハッキリと名乗る③相手の名前を復唱確認する「〇〇様でいらっしゃいますね」④名前、連絡先、用件をメモする
などです。
予約フォームやFAQの導入で“電話を受けすぎない仕組み”をつくる
HPに予約フォームやFAQを導入することで、電話の量を減らす仕組みを作ることも大切です。
例えば、新規顧客が既に電話で問い合わせを行った後、検討の末に相談予約をしたい場合、予約フォームがあれば改めて電話をする必要がなくなります。
その他、HPでFAQが提示されているのであれば、「料金だけ聞きたい」や「以前電話した時に聞きそびれた」という人の入電数を減らすことができます。
入電数が減れば、目の前の業務へ集中できる時間が増えます。
税理士の開業初期には電話代行サービスがおすすめ
開業初期の税理士事務所が電話代行サービスを利用することで、電話対応のリスクを回避することができます。
電話代行サービスは、事務所の電話をプロのオペレーターが代行して受電してくれるため、基本的に「出先で電話に出られなかった」や、「電話に出るのが遅れた」という機会損失が発生しません。
また、事務所の電話は全て電話代行サービスへ転送されるため、目の前の業務へ集中することができ、生産性を高めることができます。勧誘電話は受電しなくて良くなり、必要な電話のみ折り返しの電話を行えば良いことになるため、優先順位をつけた仕事ができるようになります。
一人税理士であっても、まるで事務員を雇っているかのような対応ができる点もメリットと言えるでしょう。
電話代行サービスなら「CUBE」
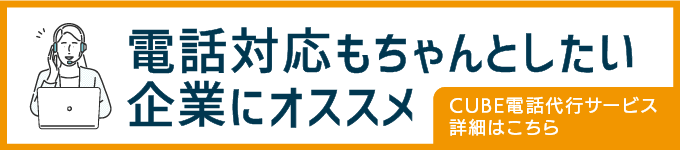
CUBE電話代行サービスは、多くの税理士の方にご利用いただいております。半年以上の研修や教育を受けたオペレーターは、明るく丁寧な対応はもちろんのこと、税理士事務所ならではの専門用語の聞き取りもスムーズに行うことができます。
また、臨機応変な対応が魅力です。
例えば、税理士の方の日々のスケジュールにあわせた応対が可能です。午前中は外出応対を行い、午後は税理士の方のスマホへ内線感覚で電話を取り次ぐなどもできます。
詳しくは是非こちらをご覧ください。
税理士・会計事務所向け電話代行サービス
電話での問い合わせ:0120-888-108
まとめ
開業時は何かとやることが多く、電話対応まで手が回らない税理士の方も多いのではないでしょうか。
しかし、電話対応をないがしろにしてしまうと、今後の事務所経営にも差し障りがでてしまうことがあります。
もし開業時に電話対応でお困りのことがあれば、電話代行サービスが大変便利です。長期的に利用される方だけではなく、事務員を雇うまでの間、とにかく今月だけ!という利用も可能です。
人を直接雇うわけではないため、気軽に始めて気軽に解約ができるという点もメリットと言えるでしょう。
電話代行サービスを検討される方は、税理士事務所の電話対応に慣れた電話代行サービスや、応対品質が良いと言われている電話代行サービスがおすすめです。
少しでも電話代行サービスに興味を持たれた方は、CUBE電話代行サービスにお気軽にご相談ください。お問い合わせのみも歓迎です。