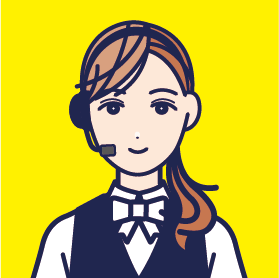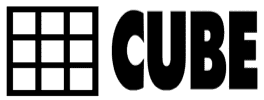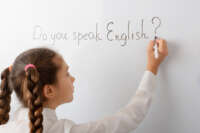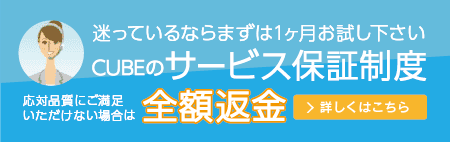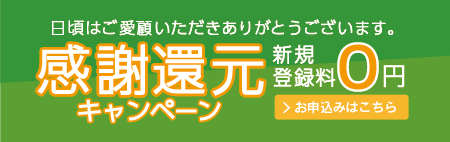日弁連のHPを確認すると、2025年8月1日時点で、日本の弁護士数は47,028人とのことす。
そして、弁護士白書2024年版では、おおよそ6割の弁護士が独立していることがわかります。
独立していない弁護士の方の中には、ゆくゆくは独立したいと思っている、もしくはすぐにでも独立したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、独立にはリスクが伴い、不安や悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな独立を考えておられる弁護士の方に向けて、弁護士の独立で多い悩みや失敗例、そして解決策を解説していきます。
参考:
日弁連の会員
【目次】
弁護士の独立はリスクが高い?

果たして弁護士の独立はリスクが高いのか、就業形態から確認してみましょう。
各年代の弁護士白書を確認すると、全体の半数以上の弁護士が独立しているということがわかります。
独立して1人事務所で仕事を行っている弁護士の割合は、ここ数年間を見ても増加傾向にあります。2022年では61.61%、2023年では61.82%、2024年では61.92%という結果でした。
また、2023年の弁護士実勢調査によれば、1人事務所に限らない経営弁護士は64.6%にのぼり、そして司法修習期別でみれば、司法試験に合格後10年以内に4割もの弁護士が独立していることがわかります。
もし、独立自体があまりにリスクが高すぎる場合、調査結果のよう経営弁護士が半数を超えることは考えにくいと言えるのではないでしょうか。
参考:
弁護士白書第三章2022年
近年の弁護士数
近年の弁護士数は年々増加しています。日本弁護士連合会の弁護士白書の年代別の弁護士数の表を見ると分かりやすいため、引用させていただきます。

近年の数年間を見るだけでも、2022年では44,101人、2023年では44,916人、2024年は45,808人と、毎年確実に弁護士数は増加しています。
そして記事の冒頭でもお伝えした通り、2025年は8月時点で47,028人ですので、過去、一度も減少することがなかったとわかります。
引用元:弁護士白書2024年版
弁護士の独立で多い悩み・失敗と対策
半数以上の弁護士が独立しているとはいえ、誰しもが独立して成功するとは限りません。
弁護士の独立で多い悩みや失敗にはどのようなものがあるのか、具体的にご紹介していきます。また、対策についても考えていきましょう。
・初期費用をかけすぎた
・運用コストがかかりすぎる
・開業資金を用意できない
・集客ができない
・方向性が定まっていない
・報酬・無料相談など依頼者に合わせすぎている
・立地選びが悪い
・事務所内でのトラブル
・以前所属していた事務所とのトラブル
初期費用をかけすぎた
まず、独立をするにあたって下記のような初期費用が発生します。
・事務所の賃料、保証金など
・内装工事費
・デスクやキャビネット、OA機器等の購入費
・インターネット回線の工事費、回線費
・事務用品の購入費
・HP制作費や広告費など
特に貸事務所を利用する場合は、小規模オフィスタイプでも保証金が賃料の3か月分~6か月分かかるところがほとんどです。賃料と保証金は、初期費用の中で一番費用がかかると言えます。また、内装費やオフィス家具もこだわると高額になってしまいます。
対策
貸事務所であればオフィス家具やOA機器、インターネット回線など全て自分で用意しなければなりません。
しかし、守秘義務を守ることができるなどの要件を満たすレンタルオフィスであれば、オフィス家具やOA機器、インターネット回線、電話回線など全てが揃った状態でオフィスを借りることが可能です。
貸事務所より執務スペースは狭くはなってしまいますが、レンタルオフィスは利便性の高い場所であることが多い点もメリットです。
その他、可能な場合は自宅開業も選択肢の1つです。自宅開業の場合は、賃料や保証金が一切発生しない点がメリットですが、自宅が日弁連のHPなどで必ず公開されてしまう点で注意が必要です。
運用コストがかかりすぎる
初期費用はなんとかなったけれども、毎月の運用コストがかかりすぎてしまうという場合もあります。
運用コストには、主に下記のようなものがあります。
・賃料
・人件費
・宣伝広告費
・交通費
・通信費
・弁護士会費
・法律データベース使用料
・消耗品購入費
・その他(交際費、研修参加費など)
賃料と人件費がランニングコストとしては高額になります。賃料は初期費用の項目でご紹介したように自宅開業であれば、抑えることができます。レンタルオフィスは、初期費用は抑えられますが、月額費用は高額になるケースもあるので注意が必要です。
人件費は、賃料とは違って必須項目ではないため、事務員を雇うか否かで大きく異なります。事務員を雇えば経費がかかる点、そして一度雇ってしまうと解雇することはすぐにはできないという点でデメリットがありますが、事務作業を任せることができるため、受ける仕事量を増やすことができる点は大きなメリットと言えるでしょう。
対策
賃料に関しては、払い続けられる金額である必要があります。立地条件などが良ければ良いほど賃料も高くなるため、ある程度は妥協する必要があります。
もしくは、初期費用の項目でお伝えしたように、レンタルオフィスを選択することも対策の1つです。レンタルオフィスはオフィス賃貸よりも狭く坪単価も高くなりますが、立地条件やグレードが高いビルに総額では安く利用出来ます。ただし、利用が増えることで従量課金も高くなり総額が高くなるケースもあるので注意は必要です。
人件費に関しては、事務員は必ず必要だと考えている場合でも、ある程度の収入を得られるまでは事務員を雇わないということでコストを大幅に抑える、という選択肢があります。
もしくは、電話代行サービスや事務代行サービスを利用するなどの工夫が必要です。
法律事務所は新規依頼者からの相談やアポイントは電話であることが多いため、運用コストを抑えながら顧問先を増やすべく、電話代行サービスを利用する弁護士も増えています。
開業資金を用意できない

開業すればすぐに顧客が安定的につくとは限らないため、開業資金としては初期費用だけではなく数か月分の運用費も必要です。
初期費用や運用コストにもよりますが、最低でも300万~500万程度は開業資金として用意しておく必要があるでしょう。しっかりと準備するためには、500万~1,000万円程度あることが望ましいです。
しかし、弁護士になってから即独立する方や、独立をするまでに何年も待てないという方など、開業資金を十分に用意できないこともあります。
対策
すぐにでも独立したいが開業資金があまり用意できないという方には、融資を受ける、もしくは事業ローンを組むという選択肢があります。弁護士協同組合が提供する融資制度がいくつかあります。また、日本政策金融公庫からの融資を受けることも可能です。
その他に、まずは自宅開業をするという選択肢もあります。自宅開業をして初期費用と運用コストを抑えることで、独立しながらも賃貸オフィスを借りるための資金を貯めることが可能になります。
関連リンク:
弁護士が独立する際に必要な準備は?タイミングや資金計画など開業のコツを解説
関連リンク:
【資金調達の方法】起業家を支援してくれる3つの融資制度(新規創業融資・制度融資・マル経融資)
集客ができない
独立後、何もしなくとも顧客が相談に来るというわけではありません。
しかし、何かしらの集客活動を行っているにも関わらず、思うように顧客がつかない場合は、集客方法が合っていない、もしくは成果が表れるまでに時間がかかる方法である可能性があります。
例えば、広告ならば、広告内容は事務所の方針や雰囲気と合っているのか、掲載場所はターゲット層が見る場所なのかどうか、しっかり検討した上で掲載する必要があります。
その他、HPの内容は他の法律事務所と差別化を図れているのかも重要です。せっかく広告をクリックしてHPを見てもらっても、相談者の気持ちが動かなければ、問い合わせまで繋がらないからです。
対策
まず事務所のHPをしっかり作成することが大切です。新規の相談者が閲覧し、相談するか否かを決める大切な窓口の1つですので、得意分野や特徴、事務所の場所、相談料など、分かりやすさは大切と言えるでしょう。
法律相談を迷っている人向けに、有益な情報をHPに載せておくことで閲覧数を増やすという選択肢もあります。
次に、HPのSEO対策を行う、MEO対策を行う、ポータルサイトへの登録やWEB広告の出稿などが考えられます。いずれも労力や金銭的負担は大きくなりますが、集客につながりやすいと言えます。
その他、セミナーの開催や交通広告なども方法としてあります。
離婚相談であればWEB広告、労働関係の法律相談を受けるのであれば交通広告、相続相談であればセミナーでアピールするなど、得意分野によって集客方法を変える必要があります。
方向性が定まっていない
法律事務所としての方向性が定まっていないまま独立することは大きなリスクを伴います。他社との差別化を図るためにも、セールスポイントは必ず必要です。
まんべんなくどんな依頼も受けられることも良いですが、数ある法律事務所の中で印象に残りにくいという側面があります。そして、「どこに依頼しても同じ」と依頼者に思われてしまい、相談内容の専門性が高い他の弁護士事務所を選択されてしまう可能性が高くなります。
得意分野があれば、「他の依頼も受けられますが、特に〇〇の解決は得意です」というアピールを行うことができます。得意分野に関しては少々金額が高くても、遠くても、得意な人に依頼したい人がいるはずです。
対策
事務所の方向性や特徴、強みは独立前に決めておく方が良いでしょう。アピールポイントが無ければ、どんなに集客活動を行っても依頼者は多く見込めません。
事務所の特徴や強みのほか、理念などをHPに記載するのも良いでしょう。
どうしても得意分野でのアピールが難しいという場合は、「休日、夜間対応可能」や、「電話相談可能」、「出張相談可能」など、その他のところで差別化を図る方法もあります。
報酬・無料相談など依頼者に合わせすぎている

依頼者に合わせすぎることで、忙しいのに収入がほとんどないという状態に陥ってしまうことがあります。
着手金無料や相談料無料であることは、依頼者や相談者にはうれしいことですが、弁護士としては負担が増えるばかりで収入に繋がらないことになりかねません。特に、相談料無料の場合、相談だけして依頼はしないという人ばかりになってしまうと、事務所経営が成り立ちません。
対策
相談の間口を広げることは集客方法の1つではありますが、経営破綻しないためにも一定のラインを決める必要があります。
「無料相談は初回30分のみ」や、「無料相談は〇曜日の△時以降、事務所にて」など、ある程度の制限を設けておくことが大切です。
また、相談や問い合わせの電話連絡が入った際に、弁護士が外出していて誰もいない…ということが起こらないように、事務員を雇う、もしくは電話代行サービスを利用するなどの対策も必要です。
立地選びが悪い
初期費用と運用コストに大きく関係する立地選びですが、いくら安くても交通の便が悪すぎるような場所はやはり集客は難しくなります。事務所のブランドにも影響があります。
しかし、利便性や知名度のある立地やグレードの高いビルであれば、どうしても賃料が高くなります。
顧客からのアクセスの良さ以外にも、事務所から裁判所や弁護士会までの距離など、仕事でよく行く場所への利便性も考慮する必要があります。
対策
初期費用と運用コストの項目の話と重複してしまいますが、立地条件を優先するのであればレンタルオフィスが有効活用できます。立地条件が良い場所で、賃貸オフィスよりもリーズナブルな料金で部屋を借りることができます。
開業場所はコスト面に大きな影響を与えるため、比較検討して立地条件とコスト面で納得できる場所を探すほかありません。
事務所内でのトラブル
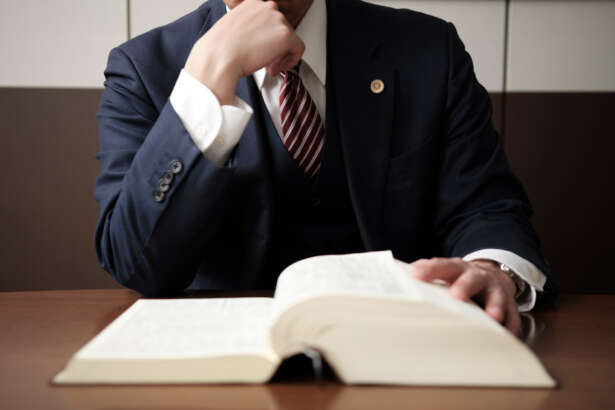
開業時から事務員を雇う方もいれば、ある程度の安定的な収入を得られるようになってから事務員を雇う方もいます。事務所が大きくなってくれば、弁護士を増やす可能性もあるでしょう。
しかし、人が増えると人間関係のトラブルが増える可能性が高まります。
こちらが意図していなくとも、十分なコミュニケーションが取れていない場合、事務員から「言い方がキツイ」や「話しかけにくい」などの不満を抱かれてしまう可能性もあります。
不満が大きくなってしまうと、指示が上手く通らなくなるだけでなく、最終的に退職してしまうことにもなりかねません。
対策
顧客に対して気配りを行うのと同様に、事務所内でもコミュニケーションや気配りは必要です。意思疎通がうまくいかなければ、効率的な仕事は行えません。逆に、事務所内のコミュニケーションが円滑であれば、仕事の指示も通りやすいと言えます。
事務所内での密なコミュニケーションがどうしても苦手な場合は、事務員を雇わずに事務代行サービスや電話代行サービスに依頼する方法もあります。
以前所属していた事務所とのトラブル
即独立の弁護士以外は、どこかの法律事務所に所属していた方がほとんどではないでしょうか。
法律事務所に所属していた弁護士は、独立するために退職をする必要がありますが、この退職の申し出や手続きでトラブルになることがあります。
具体的には、退職の申し出から退職までの期間があまりに短い場合、十分な引継ぎが行えなかったり、クライアントから不信感を抱かれたりする可能性が高く、今までお世話になった事務所が不利益を被ることになりかねません。
また、すぐに退職してしまっては人員補充も間に合わないため、トラブルに発展する可能性が高くなります。
対策
まず、退職する月の3カ月から6カ月前には事務所に口頭でハッキリと申し出ておく必要があります。もちろん、7カ月前でも8カ月前でも、早く申し出る分には良いでしょう。
基本的には退職するにあたって、担当している案件は全て他の弁護士に引き継ぐことになると思いますが、独立後もそのまま担当できるかどうかの確認も必要です。
事務所と信頼関係を保ったまま退職することができれば、独立後にクライアントを紹介してくれる可能性もあります。
弁護士・法律事務所向けの電話代行サービスならCUBE

CUBE電話代行サービスは、弁護士・法律事務所向け電話代行サービスの「My Team108」を提供させていただいております。
「My Team108」では、弁護士の方のその日のスケジュールに合わせて、「外出応対」や「相談対応中応対」、「席外し応対」、そして内線感覚で電話をスマホに繋ぐことのできる「応答後転送」をご利用いただけます。
外出しているタイミングでは、CUBE電話代行サービスのオペレーターがしっかりと、そして親切丁寧に電話相手のご用件を伺いますので、新規顧客獲得の機会損失を防ぐことができます。
また、オペレーターは半年以上の研修や教育を受けた正社員にて構成されており、どのようなお電話にも臨機応変に落ち着いた対応ができるため、顧問先からの信頼関係をより強くすることが可能です。
まとめ
本記事では、弁護士の独立で多い悩みや失敗、そしてその解決策を解説してまいりました。
独立にはリスクが伴いますが、しっかりとした準備と計画、そして便利なサービスを上手く利用することで必要以上に不安になる必要はなくなります。
便利なサービスの1つに電話代行サービスがありますが、実際に独立後に電話代行サービスを利用する弁護士の方が多いのはご存知でしょうか。
CUBE電話代行サービスの「My Team108」でも、独立後にサービスを開始され、そのまま事務員を雇った後でも継続利用されている方も多数いらっしゃいます。
「My Team108」では、法律事務所特有の専門用語にも対応しておりますので、裁判所や役所、銀行などからの電話にもスムーズで無駄のないやり取りが可能です。
また、問い合わせや相談、依頼の方には落ち着いた丁寧な対応で、電話口から顧客満足度を向上させます。
少しでもご興味のある方は、是非お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ、相談のみでも大歓迎です。
電話番号:0120-700-108