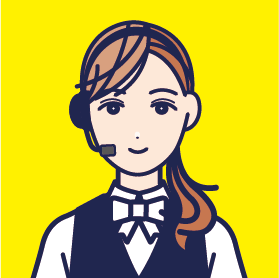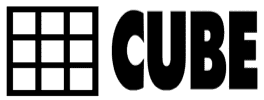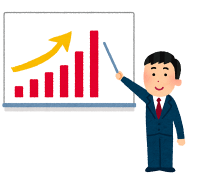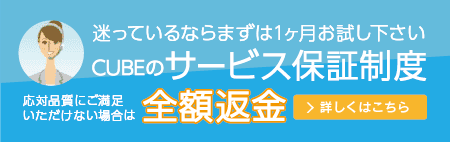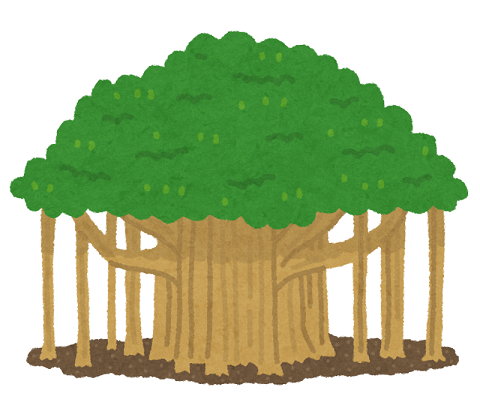
【目次】
植物の進化が教えてくれるもの
植物は樹齢1000年以上の大木もあることから、その気になれば大木となり何百年も生き続けることができると言われる。ところが、その植物は長生きする大型の木本から、短命な草本が進化をした。どうして何百年も生きることのできるはずの植物が、進化の結果、短い命を選択したのか。
予測不能なことが起きる環境では、ある一つのことが成功したからといって、次もまた同じ方法で成功するとは限らない。環境が変化をすれば、環境に合わせて生物も変化をする必要があるが、環境の変化に合わせて変化を遂げることは容易ではない。
成功した個体が長生きするよりも、多様な性質を持つ卵や種子を作って、世代交代を早める方法が、新たな環境に適応していくことができる。そのため、予測不能な環境に生きる生き物は寿命が短いのだとされている。
雑草のような生物が短い命に進化した理由もまさにここにある。長すぎる命は天命を全うすることができない。そこで天命を全うするために短い命を選択したと見ることができる。命の輝きを保つために、生命は短くも限りある命に価値を見出したのだ。(以上、「弱者の戦略」(稲垣栄洋著)より引用)
挑戦できない経営者
先日、ある企業で相談を受けた。その会社は祖父の代から続く町工場で、今はその孫に当たる中年の女性経営者が後を継いでいる。その女性経営者が曰く、始めは会社を継ぐこと自体が嫌で仕様がなかった。確かに油まみれの仕事は女性には馴染みにくいものだろう。でも小さなことから従業員と喜怒哀楽を共にするうちに、その仕事がというより、その従業員たちと仕事をすることが好きになっていったという。今では見た目順調に経営をされており、経営者の鏡のような方のようにお見受けした。
しかし、その女性経営者にも悩みはある。それを相談されたのだが、経営が順調に行くようになればなるほど、今度はもともと若いころにしたかった新しい試みに挑戦したくなったのだというのだ。それを聞いた時、私などはすぐに「それなら挑戦すればいいじゃないか。何の問題があるのか」と思ったのだが、その女性経営者にとっては、新しいことに挑戦するには資金もいるし、そのための時間も捻出しなければならない。何よりそれで従業員を食べさせていけるかどうかも分からない。「従業員を食べさせる責任があるのに、そんな冒険はできない」というのだ。
経営者の責任って何
なるほど。その女性経営者の従業員に対する責任感が、その決断を躊躇させていたのかということが分かると、むしろ普段からその軽々しさを注意されることの多い私は一瞬感動さえした。しかし、すぐに目先いくら仕事が忙しくても、それがいつまで続くのか、いつまでも続くことはあり得ないだろうということに思いが至った。経営者ならその視線を目先のところに置くのではなく、数年先、10年先、10年その先に置いて、会社を存続させなければならない。そのための挑戦を普段からしておかねば、いつするというのだろう。
確かに、十分な資金もないかもしれないし、時間もないかもしれない。しかし、それを理由に挑戦できない経営者は、たとえそれらが十分に整ったところで挑戦のできないことに変わりはないだろう。幸運の神は決して条件が整っている時に来るのではないことをしっかり思い起こすべきだ。この女性経営者の場合だと、既存の事業に影響を及ぼすことを恐れているのなら、別会社を作れば済む話だ。そして、その別会社で独立採算を目指して取り組めば良いのではないだろうか。時間がないというのはまったく理由にも何にもならない。一体やる気があるのかないのかの問題だ。

「大変革期」に生きる
トヨタ自動車の豊田章男社長は「今は100年に一度の大変革期」だと話している。天下のトヨタでさえ、非常な危機感を持って経営に当たっているのだ。まして中小企業にとって、今のままで将来も生き残ることができると本気で思っている方がどうにかしている。
初代iPhoneの発売は今からまだ11年ほど前でしかない。それ以前のiPhoneのない世界がどうだったか思い出せるだろうか。時代は想像以上に動いている。AIはどうか。IoTはどうか。ロボットは。ドローンは。それらの動きは皆さんの経営に関係ないだろうか。10年後にそれらが主役として登場している時、今の仕事はどうなっているだろうか。誰も答えなんて持っていない。誰も未来の世界を知らないからだ。でも、だから挑戦し続けなければならないのだ。
中小企業の中には先の女性経営者だけでなく、従業員の和を重んじるあまりか、将来の方向性について独自色を求めることをためらう傾向があるように思う。「そんなことをすれば、今働いてくれている従業員がついてこなくなる」というのだ。人手不足の時代だからなおさらなのかもしれない。しかし、それは逆だ。挑戦をためらっているようではこれからの経営はできない。しっかりそのことを自覚する必要があるのではないだろうか。