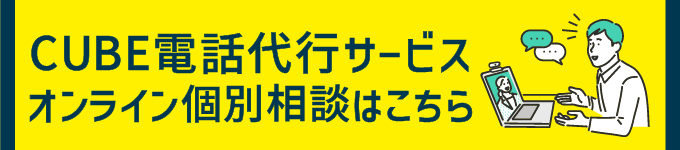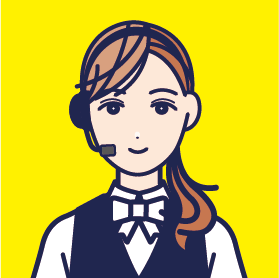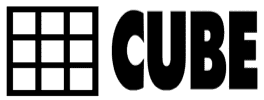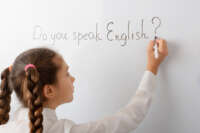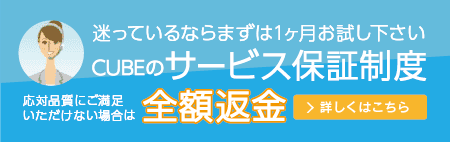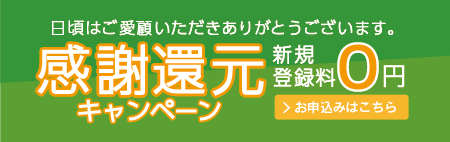電話対応で相手に好印象を与えることは、対面で相手に好印象を与えるよりも難しいとされています。
対面であれば、身だしなみや服装、表情やジェスチャーなどの視覚情報から好印象につながることがありますが、電話では言語情報と聴覚情報のみに絞られてしまうためです。
本記事では、対面よりも好印象を与えることが難しいとされる電話対応に焦点をあて、電話対応で好印象を与えるためのコツをご紹介していきます。
電話対応が苦手な方、または新人教育でお悩みの方の参考になれば幸いです。
【目次】
電話対応の基本の心構えとは?

自社に「自分宛の電話でなければ、相手に好印象を与える必要はない」と考える従業員がいる場合、「電話は企業の顔」であることを改めて伝える必要があります。
ビジネスでは、「個人の発言や態度」ではなく、「企業全体の発言や態度」とみなされるためです。
顧客や取引先は、電話に出た相手の発言や態度、聴覚情報で得られるすべてを「企業全体の印象」としてみているということです。
従業員の話し方が「冷たい」「粗暴だ」と感じれば、それはつまり、その企業から冷たくて横柄な対応をされたと感じます。
逆に、従業員に「明るく」「丁寧に」対応されたと感じれば、その企業から丁重に扱ってもらったと感じます。
このように、ビジネスにおいての電話対応では、どのような電話内容であっても「企業の代表として対応している」ということを、従業員全員が共通認識として持つことが大切です。
第一印象を決める3秒間の対応方法
カリフォルニア大学ロサンゼルス校の心理学名誉教授のアルバート・メラビアンが発表した「メラビアンの法則」では、第一印象は最初の3~5秒で決まるとされています。
ということは、電話対応では、第一声の挨拶でほぼ第一印象が決まるということです。
3秒~5秒までの具体的な流れとしては、下記のような手順です。
① コールが鳴る
② 受電する
③ 挨拶と名乗りを行う
「ありがとうございます。〇〇株式会社の△△(名前)でございます」
この挨拶と名乗りでは、明るく、はきはきした声で、聞き取りやすいスピードを意識します。
具体的には、姿勢を正して口角を上げ、普段の話し言葉よりもゆっくりとしたスピードで話します。
そして声のトーンは普段よりもワントーン上げることで、明るくはきはきした、聞き取りやすい挨拶が行えます。
ほかにも、平坦な話し方では冷たい印象を持たれてしまうため、語尾は伸ばさずに、言葉に抑揚をつけると良いでしょう。
即座の対応で信頼感を高める方法
第一声の挨拶と名乗り出第一印象を印象良くすることはとても重要ですが、その前に気をつけなければならないことがあります。
それは、受電するまでにかかる時間です。
電話は1コールがおおよそ3秒程度であり、一般的には受電までに3コール以上鳴らさないことがマナーとされています。
鳴らしてしまった場合は、「お待たせいたしました」もしくは「大変お待たせいたしました」と第一声でお詫びします。
なぜなら、多くの人は電話をかけた時、10秒以上待たされると「長く待たされている」と感じるためです。中には待ちきれずに電話を切ってしまう人や、不快に感じたり、怒ったりする人もいるでしょう。
逆に、コールが鳴ってすぐに対応することは、「素早い対応が出来る企業」「顧客を待たせない企業」というイメージに繋がり、安心感や信頼感を高めることができます。
電話対応での声のトーンと話し方のコツ
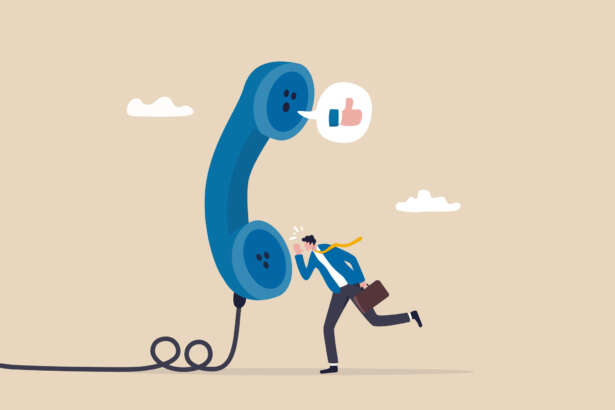
電話相手に好印象を与えるためには、声のトーンや話し方は重要です。
既述した「メラビアンの法則」では、相手の印象を決める情報のパーセントとして、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%だとされています。
しかし、電話対応では、最も多い視覚情報が無く、聴覚情報と言語情報でしか相手の印象を判断できません。
ということは、「何を言っているか」という言語情報よりも、「どのような声のトーンや話し方、話すスピードで言っているか」という聴覚情報でほぼ判断されるということです。
例えば、同じ挨拶を行っても、声のトーンやスピードが違うだけで印象の持たれ方は大きく異なります。
声のトーンが高ければ、「明るさ」「元気さ」という印象を与えやすくなます。声のトーンが低ければ、「落ち着いている」という印象を与え安くなります。
しかし、どちらにせよ話し方に抑揚が無ければ「冷たい」という印象を与えかねませんので注意が必要です。
相手に合わせた声のトーンの調整法
第一声の挨拶は「対面の会話よりワントーン高くする」ことが大切ですが、高すぎても聞き取りにくいため加減が必要です。
具体的には、ドレミファソラシドの「ソ」の音の高さが基準です。
挨拶の声のトーンが一番高く、そこから声のトーンを少しだけ落としてゆったりと話すことで、「明るく丁寧」な印象と、「落ち着いた安心感」のある印象を与えることができるでしょう。
重要な話やクレームに対してお詫びを行う際は、低めの声のトーンで、ゆっくりと、そしてしっかりとした敬語で話すと、相手に「真剣な話である」と聴覚情報で伝えることができます。また、謝罪の気持ちが伝わりやすくなります。
世間話などの場合は、声のトーンは高めに少し早いテンポで話すと、元気な印象を与えながらも「覚えておかなくてよい内容」として聴覚情報で伝えることが可能です。
好印象を与える抑揚のつけ方
話し方に抑揚がなければ単調に聞こえてしまい、大切な用件であっても相手に伝わりにくくなってしまいます。また、抑揚が無いことで「冷たい」という印象を与えてしまいかねません。特に、クレーム対応の場合、お詫びしていても抑揚が無いことで「悪いと思っていないだろう!」とさらに相手を怒らせてしまう可能性もあります。
好印象を与える抑揚のある話し方を行うには、一文を発するときに山なりになるイメージで、語尾は下げます。

難しければ、語尾を下げるだけでも良いでしょう。
ただし何かを問いかける疑問文の場合、語尾は上がります。
また、会話の中で強調して伝えたいところはゆっくりと、そしてはっきりと伝えることで、メリハリがついて伝わりやすくなります。
好印象を与える電話の言葉遣い

これまでは主に聴覚情報での印象について解説してきましたが、言語情報で受ける印象も忘れてはいけません。声のトーンや抑揚をしっかり調整できても、言葉遣いが悪ければもちろん印象は悪くなります。
好印象を与える言葉遣いをするには、「ビジネスで使う定型文」や「正しい敬語」、「クッション言葉」を知っておく必要があります。
例えば、架電者側が名乗る場合は、下記のような定型文を使います。
「お世話になっております。●●事務所の△▽(名前)と申します」
それを聞いた受電側は、下記のような定型文で挨拶を返します。
「△▽様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております」
覚えてしまえば難しいことではありませんが、知らなければ無意識に失礼な言葉遣いをしている可能性があります。
その他、「正しい敬語」、「クッション言葉」についてもご紹介します。
電話での効果的な敬語表現
正しい敬語を使いこなすのは意外と難しいのですが、電話で使う頻度が高い敬語に焦点を絞って覚えると効果的です。
まず、敬語には大きく分けて「丁寧語」と「謙譲語」、「尊敬語」があります。丁寧語は「です」「ます」などの広範囲で使える敬語です。
謙譲語は「自分がへりくだることで相手を立てる」言葉で、尊敬語は「相手を敬い、相手の行動や言動を立てる」言葉です。
電話で使う頻度の高い敬語を、謙譲語と尊敬語に分けて表にまとめてみました。
| 敬語の種類 | 元の言い方 | 敬語に変換 | 活用事例 |
| 謙譲語 | 自分の会社 | 弊社 | 後日、弊社の新商品をお送りします。 |
| 聞く | 伺う・承る | ご用件を承ります。 | |
| 言う | 申し上げる | 心よりお礼申し上げます。 | |
| ごめん | 申し訳ございません | お待たせして申し訳ございません。 | |
| わかった | 承知しました | ~~の件、承知しました。 | |
| 尊敬語 | 相手の会社 | 御社 | 後ほど御社にお伺いします。 |
| いる | いらっしゃる | 〇〇様はいらっしゃいますか。 | |
| 来る | いらっしゃる | 弊社まで車でいらっしゃいますか。 | |
| 見る | ご覧になる | お手元の資料をご覧いただけますか。 |
心をつかむクッション言葉の使い方
クッション言葉を効果的に使うことができれば、相手の心をぐっと掴むことができます。
逆にクッション言葉を使わなければ、相手が不快に思うこともあります。
電話で使う頻度が高いクッション言葉を表にまとめました。
参考になれば幸いです。
| クッション言葉 | 使用例 |
| 恐れ入りますが | 恐れ入りますが、ご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか。 |
| お手数をおかけいたしますが | お手数をおかけいたしますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。 |
| あいにくではございますが | あいにくではございますが、〇〇はただいま外出しております。 |
| 申し訳ございませんが | 申し訳ございませんが、明日は終日不在にしております。 |
| 差し支えなければ | 差し支えなければ、ご連絡先をお伺いしてよろしいでしょうか。 |
電話対応でよくある失敗と対処法
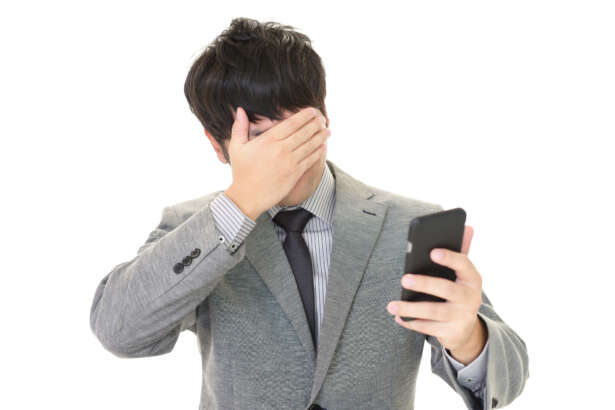
電話対応でよくある失敗を事前に知っておくことで、ミスが防げることがあります。
電話対応でのよくある失敗は大きく2つにわけることができます。
「聞き取り間違い」と「曖昧な返事で誤った情報を伝える」です。
聞き取り間違いは、相手の社名や名前、電話番号、日付や曜日、金額などで起こりやすいです。対処法としては、間違いやすい項目は必ず復唱確認をすることです。
例えば、「××商事の◇◇様でいらっしゃいますね」や、「お電話番号は、000-0000-0000でお間違いないでしょうか」などと声に出して相手に確認をとると良いでしょう。
曖昧な返事はミスやトラブルに直結します。
よく理解していない用件や、わからない話に関しては安易に「そうですね」や「はい」や「恐らく」などと言わないことが対処法と言えるでしょう。
「詳しい者に電話を代わります」や、「確認いたしますので少々お待ちください」、「確認して後ほどご連絡させていただきます」など、わからない時に使える定型文を覚えておくと良いでしょう。
クレーム対応で陥りやすい3つの失敗と適切な対処手順
クレーム対応においても失敗は起こりえます。クレーム対応でのよくある失敗を大きく3つにわけると、「相手の話を最後まで聞かない」、「謝罪をしない」、「何に対して怒っているのかわからない」があります。この3つは1つでも当てはまると、さらなるクレームに発展します。
【相手の話を最後まで聞かないという場合】
「こちら側は悪くない」という気持ちが原因で起こる失敗と言えます。
相手の勘違いや解釈違いで起こるクレームであっても、まずは相手の話を最後まで話を聞くことが大切です。
途中で「いや、それは違います」や「そうは言いますが」などと言って話をさえぎってしまうことにより、相手は「話を聞いてくれない」という更なる不満が発生します。
何を勘違いしたのか、どのような解釈違いが起こったのかを見極めるためにも、話は最後まで聞きましょう。
【謝罪をしない場合】
同じく「こちらは悪くない」という気持ちが大きいか、もしくは、「謝ったら非を認めたことになるから謝罪してはいけない」という考えが原因と言えます。
たとえこちらが悪くない場合でも、「不快な思いをさせてしまったこと」に対してのお詫びは必要です。こちら側に非が無い場合は、部分的な謝罪を行うと良いでしょう。
もちろん、しっかりと気持ちを込めたお詫びが必要です。
【何に対して怒っているのかわからない】
聞き手が話を整理できていないことが原因と言えるでしょう。怒っている人は感情的に話を展開するため、時系列が分かりにくい場合があります。メモを取ったり、復唱確認をしたりして、聞き手がしっかりと話をまとめていく作業が必要です。
そして、「~~にお困りだったということですね」など、相手がどこに対して怒っているのかを理解し、共有することが大切です。
電話代行サービスなら「CUBE」
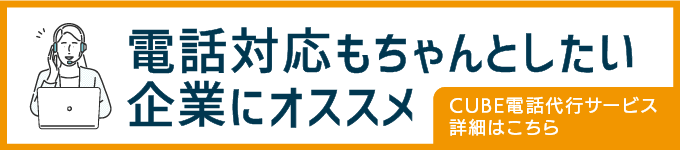
CUBE電話代行サービスは、6カ月の教育と研修を受けたプロのオペレーターが電話対応を行います。明るく丁寧、そして臨機応変な対応をモットーにしており、電話相手に好印象を与えます。
クレーム一次対応も基本料金内で行っているため、安心して利用していただけます。
まとめ
電話対応で好印象を与えるためには、聴覚情報と言語情報でそれぞれトレーニングが必要です。時間はかかるかもしれませんが、マニュアルなどを利用したり、ロールプレイングなどを行ったり、実際の会話を録音して聞き直すなどしてみると良いでしょう。
そんな時間は無い!とお困りの方には、電話代行サービスがおすすめです。
CUBE電話代行サービスでは、ご契約いただいた企業の代表電話に対して教育を受けたオペレーターが明るく丁寧に対応します。オペレーターは秘書検定と電話応対技能検定の2つの資格を取得している正社員のため、質の高い安定した電話対応を行うことが可能です。
少しでも気になる方は、是非お気軽にお問い合わせください。
ご相談のみも歓迎です。