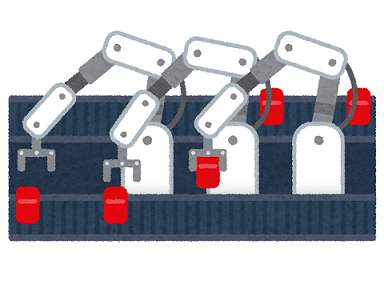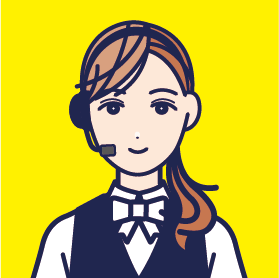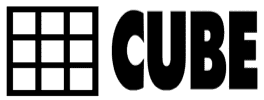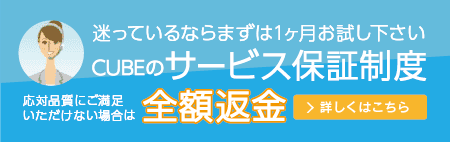【目次】
蟻の隊列にはなぜ渋滞がないのか
「渋滞学」という学問が注目されている。渋滞というと、普通は車の流れを思い起こす。その流れが悪くなるのが渋滞だが、典型的な例として挙げられるのが、運転手が気づかないくらいの緩やかな坂道を上る時。少しずつ車の速度は落ちていくが、その時、後続車が早く行きたいために車間距離を詰めて走っていると、追突を避けるためにブレーキを踏むことになる。さらにその後ろの車も詰めて走っていれば、その車はより強くブレーキを踏まなければならなくなる。そうして後続車にブレーキが続くことによって、数十台後には止まらざるを得なくなるのだ。
それがコンピューターによる計算や実証事件を経て、あえてゆっくり走り、車間距離を空けて走ることで渋滞を未然に防ぐことができ、たとえ渋滞になった時でもすぐに解消できることが分かったというのだ。要するに、短期的には車間距離を詰めて走った方が早く目的地に行けるように思えるが、長期的には交通渋滞を引き起こし、逆の結果を招いてしまうという。ちなみに、蟻の行列の一匹一匹は車間距離ならぬ「蟻間距離」を取っているそうだ。だから蟻の世界に渋滞はないのだそうだ。

渋滞学は車だけの問題ではない
ここまでなら、毎日の通勤や特に盆や暮れの帰省ラッシュの参考に聞いていれば済むのだが、この渋滞学はいろいろなところで応用されつつある。車を人の流れや、物流など工場の中でモノを生産している場合などのように、何かが溜まっていたり、在庫や売れ残りなどに置き換えるとどうなるか。もともとこの渋滞学を起こした東大の西成活裕教授は流体力学の研究者で、「自然の流れを社会科学の流れに適応したら面白いのではないだろうか」という発想で生んだのが発端だったという。
例えば、成田国際空港の入国審査。海外から帰ってきた時、日本人の入国は早いのだが、外国人の場合は20分くらい並ぶこともあって、待ち時間をどうにか短縮できないものかという課題があった。これには飛行機が空港に到着した後に入国審査のカウンターまで歩いて並ぶという搭乗客の流れに対し、降りてくる客の数に合わせて係員の人数を最適化するというプログラムを作って対応したそうだ。
売り上げだけを上げても利益に直結するとは限らない
実際にあった企業での例としては、ある企業で営業部門が頑張って売り上げを3倍にしたことに対して、大きな評価が与えられていた。まあ当然そうなるだろう。しかし、全社的な視点で見ると、突然に営業部門が大きな売り上げを上げたために、調達や物流部門の体制が整わず、結果的には営業部門の成果を上回る損失につながったというのだ。こんな場合、調達や物流部門に対して、ハッパをかけて、営業部門の成果を活かすことのできなかった責任を押し付けているだけでは能がない。
損失の原因は、営業部門が自部門だけの成績のことしか考えず、部門間で十分なコミュニケーションを取らないままに、目先の成果を出すために行動したことが組織の「渋滞」を招いたと考えらえるのだ。それは個人の間でも同じだ。一部の真面目な社員がどんどん仕事を進めても、別の社員がその作業に対処できなければ、そこにも渋滞が生じることになる。そのような事態を招かないためには、やはり長期的な視点に立って、自分や自部門だけの利益を追う「部分最適」ではなく、「全体最適」の視点で仕事や経営に取り組むことが必要になってくる。
経験値や慣習を見直すきっかけに
そのためには、今一番大事な目的は何か、今やる必要のない無駄なことは何かを全社で話合い、共有することが求められる。それがきちんと共有されておれば、例えば「今は営業部門は頑張らなくていい。その分、調達と物流部門に経営資源を振り向けよう」といった判断を下すことができる。それが長期的に見た時に無駄のない仕事をしていることに繋がるのだ。
工場などで使われる機械設備は稼働率100%を目標にすると、長期的に見て機械の調子が悪くなった時に生産性が下がる事態が予想される。むしろ80%程度でメンテナンスをしながら使う方が利益が上がることが経験上分かっている。
顧客に提供するサービスのレベルにしても、経営の合理化の必要性に迫られて、思い切ってレベルを下げてみたところ、顧客からのクレームもなく合理化との両立がかなったということもある。これまでの経験値や慣習でよかれと思って行っていたことが、実は企業の生産性を損なっていたというケースは多い。
渋滞学が私たちに教えてくれるのは、まずこの長期的な視点の大切さではないだろうか。