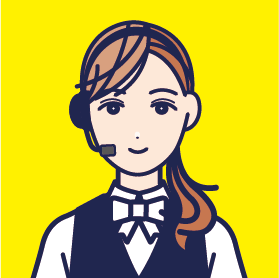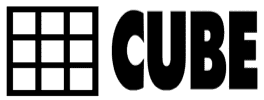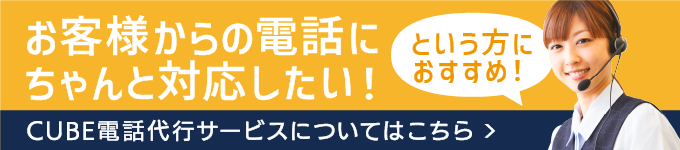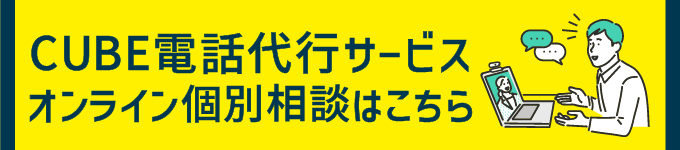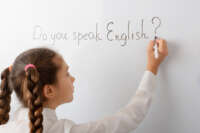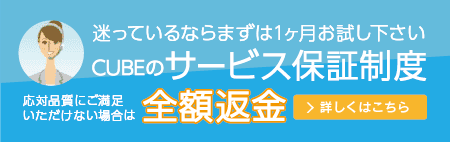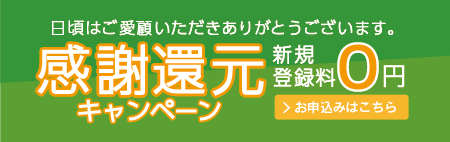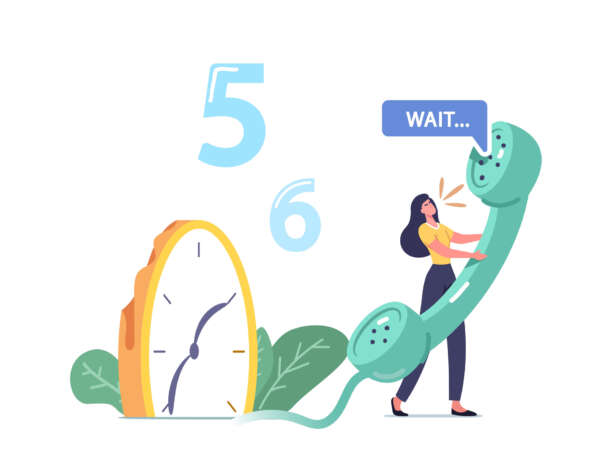
オフィスで電話対応を行う際に、電話を保留にした経験は誰しもあるのではないでしょうか。
しかし、電話の保留のマナーを知らずに保留対応をしてしまうと、電話相手を不快にさせてしまう恐れがあります。
例えば、「保留を解除したら電話相手が不機嫌になっていた」または、「なぜか電話相手に怒られてしまった」などの経験がある方は、知らずにマナー違反を行っていた可能性が高いと言えるでしょう。
自身の対応がマナー違反になっていないか不安がある、もしくは、自社に保留のマナーを知らないスタッフがいるという方に向けて、本記事では電話対応における保留のマナーをご紹介します。
【目次】
保留を行う目的
そもそも電話対応の保留は、どのようなときに必要なのでしょうか。
電話対応の保留とは、自分宛ではない電話を取った時や、その場ですぐに回答できない話になった時に行います。
基本的には、保留中に課題解決、問題解決の準備をします。
課題解決の準備中に保留をしなければ、社内の会話や雑音がすべて電話相手に聞こえてしまうため失礼にあたります。
そのため、保留を行うこと自体は正しい電話対応のマナーです。
具体的には、保留中には下記のような行動をとることがほとんどです。
・名指し人が在席しているか確認する
・在席している名指し人に電話を代わってほしいと依頼する
・自分自身では対応できないため、担当者に電話を代わってほしいと依頼する
・自分自身で回答するために、資料などを確認する
・自分自身で回答するために、上司や担当者に確認を取る、相談をする
適切な保留時間とは?

保留対応自体は相手に雑音を聞かせないための正しい電話マナーですが、保留時間が長くなってしまうと相手は「待たされている」「対応が遅い」という気持ちがどんどん大きくなってしまいます。
具体的には30秒以上待たされると人はイライラしてしまい、クレームにつながりやすくなると言われています。
そのため、保留中は30秒という時間を意識する必要があります。
保留時間を短くする方法
保留時間が長ければ長いほど、相手を不快にさせてしまう可能性が高まります。そのため、なるべく保留時間を短くするための工夫が必要です。
本記事では、保留時間を短くするための方法を具体的に5つご紹介します。
1. 状況別の保留対応を意識しておく
2. よくある質問を整理しておく
3. 迅速な情報検索体制を整える
4. 関連部署や担当者へのスムーズな連絡手段を確保
5. 折り返し連絡するよう伝える
状況別の保留対応を意識しておく
状況によって保留対応の方法は異なります。
例えば、自分以外の担当者に電話を代わる場合、自分で調べて回答を見つける場合、上司や担当者に確認もしくは相談して回答する場合などがあります。
電話の用件や相手の状況にあわせて、保留後の対応のパターンがあることを意識しておくだけでも保留時間は大きく異なります。
例えば、顧客に「頑張れば調べて回答できそうな担当外の質問」を受けた場合、自身が調べることで保留時間が長くなってしまう可能性が高いと言えます。
この場合、すぐに担当者に電話を代わってもらったほうがスムーズだということです。
よくある質問を整理しておく
顧客や取引先からの質問に対して毎回保留をして調べるよりも、よく受ける質問はすぐに答えられるように整理しておくことで保留時間を短縮する、もしくは保留自体を無くすことができます。
そして誤った回答を行わないために、よくある質問は内容を常に最新のものとして更新することも大切です。
また、同じ部署や担当のスタッフと情報共有を行えば、よくある質問の項目をお互いに補い合うことができ、さらに保留時間を短縮することもできます。
迅速な情報検索体制を整える
たとえば顧客リストや受発注履歴、その他商品情報など、目視で1つずつ上から探すとなると大変な時間がかかります。
しかし、システムで迅速に検索できる状態であれば、保留時間を大幅に短縮することができます。
もしよく使うリストや履歴がPC上の別々のフォルダなどに保管されている場合は、同じフォルダ内に保存しておくことや、ショートカットを作成する等も方法の1つです。
その他、システムで検索するにあたってログインが必要な場合は、電話対応を行う前にログインしておくことで時間短縮が図れます。
関連部署や担当者へのスムーズな連絡手段を確保
電話の用件や状況によっては、関連部署や担当者へ電話を繋いだり、確認を取ったり、相談を行う必要があります。
その際に、関連部署や担当者の内線番号がわからないとなると、内線番号を調べるための保留時間が発生してしまいます。
内線番号の一覧表などは見えやすい位置に保管しておく、もしくはデータ上ですぐに検索できる状態で電話対応を行うと良いでしょう。
よく内線をかける相手がいる場合は、ビジネスフォンの短縮ダイヤルに内線番号を登録することも有効です。
折り返し連絡するよう伝える
顧客や取引先からの質問に対して確認に時間を要する場合は、保留対応をせずに折り返しの連絡を提案する方法があります。
たとえば、「確認にお時間をいただくため、わかり次第こちらからお電話差し上げてもよろしいでしょうか」等、電話相手に提案します。
電話相手は回答を待っている間、保留音を聞きながら待つのではなく、受話器から離れて別のことができるメリットがあります。
ただし、顧客や取引先の状況によっては、「いえ、待ちます」という人もいますので、その際は保留対応を行って迅速に確認を行う必要があります。
保留対応の種類
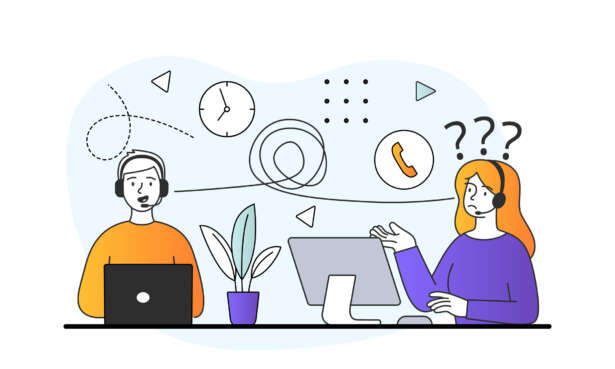
保留対応は、大きく分けて下記の3つの種類にわけることができます。
・電話を別の人に取り次ぐ場合
・調べものをする場合
・上司に相談する場合
本記事では、それぞれ保留対応の具体的な方法や時間の目安をご説明しましょう。
電話を別の人に取り次ぐ場合
自分以外の名指しの電話や、他に担当者がいる案件の用件など、電話対応では電話を別の人に取り次ぐことはよくあることです。
社内にいる担当者に内線で取り次ぐ際には、下記のような手順を踏みます。
① 電話相手に「担当者に代わりますので少々お待ちください」と伝える
② 保留をする
③ 内線番号を押す
④ 担当者に誰からどのような電話が入っているか伝える
⑤ 繋いでいいと言われてから内線を転送する
担当者が近くにいる場合は、内線転送ではなく保留で対応することも可能です。
① 電話相手に「担当者に代わりますので少々お待ちください」と伝える
② 保留をする
③ 担当者に声をかけて、内線の何番に誰からどのような電話が入っているか伝える
④ 担当者が保留を解除して話す
調べものをする場合
顧客や取引先から受けた質問や疑問に対して、その場で調べて回答するということも電話対応ではよくあります。
「適切な保留時間とは?」の項目で既述したように、調べものを行う時間はおおよそ30秒以内が目安です。
手順としては下記のような流れになります。
① 電話相手に「お調べ(確認)いたしますので、少々お待ちください」と伝える
② 保留をする
③ 30秒を目安に調べものをする
④ 保留を解除する
⑤ 「お待たせいたしました」と伝えてから、回答を行う
ここで注意したい点は、30秒経っても調べものが終わらず、回答が用意できない場合です。
その場合は、30秒ほどでいったん保留を解除し、「大変申し訳ございません。
確認に今しばらく時間がかかりますので、わかり次第折返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」と、電話相手に確認を取るようにしましょう。
更に言えば、下記のように具体的な時間を示すことができればなお良いでしょう。
「確認に時間がかかっており大変申し訳ございません。あと10分ほどお時間をいただきたいため、わかり次第、折返しお電話を差し上げてもよろしいでしょうか」
上司に相談する場合
上司の判断が必要な用件の場合、状況に応じて保留対応を行います。
調べものと同じく、おおよそ30秒で回答が得られると予想できる用件の場合は、下記のように対応します。
【上司が近くにいる場合】
① 電話相手に「確認いたしますので、少々お待ちください」と伝える
② 近くの上司に声をかける
③ 電話内容を伝えて相談をする
④ 回答を得る
⑤ 保留を解除する
⑥ 「お待たせいたしました」と伝えてから、回答を行う
【上司が近くにはいないが自席にいる場合】
① 電話相手に「確認いたしますので、少々お待ちください」と伝える
② 保留をする
③ 上司の内線番号を押す
④ 上司に電話内容を伝えて相談する
⑤ 回答を得る
⑥ 保留を解除する
⑦ 「お待たせいたしました」と伝えてから、回答を行う
もちろん、社内に上司がいない場合もあれば、近くに上司がいてもすぐに回答を得られない場合もあるでしょう。
そんなときは、電話相手にお詫びした上で折返しの電話を提案するようにしましょう。
保留対応でクレームになるケース
相手に不快な思いをさせないための便利な保留機能ではありますが、気を付けなければ保留対応が原因でクレームになってしまう場合もあります。
特に、下記のような場合はクレームに繋がる可能性が高まります。
・保留時間が長すぎる
・保留の理由を説明しない
・保留中に電話が切れる
・保留後の対応が不適切
・保留を繰り返す
保留時間が長すぎる
何度か記載している通り、保留時間が長ければ長いほど、待たされている方には不満がたまります。
保留時間が長引くと、人によっては「こんなに待っているのに担当者はいったい何をしているんだ?」や、「こんなに待っているのだから期待している回答がくるはず」という気持ちが出てきてしまいます。
目安は30秒と言われていますが、保留時間が30秒以内であればクレームにならないとは限りません。
なるべく早く保留解除を行う意識に加え、時間がかかるときは折り返しの電話を提案するようにしましょう。
保留の理由を説明しない
電話相手に理由を伝えずに保留にされてしまうと、電話相手は不安になります。
例えば、電話口で何かを質問した際に、「少々お待ちください」のみ伝えて保留をしてしまうと、なぜ待たされているのかハッキリしません。
「保留されているが相手は一体何をしているのか?」や、「もしかして忘れられているのではないか?」、「別の仕事をしているのでは?」という心理状態になります。
そして不安が強まると苛立ちに繋がり、クレームになってしまう可能性が出てくるのです。
逆にはっきりと理由を伝えれば、電話相手も待たされることに対して納得しやすくなります。
保留中に電話が切れる
意図せず保留中に電話を誤って切ってしまうことがあります。
例えば、調べ物をしていてたまたま切電ボタンに手が当たってしまったり、保留を解除しようとして誤って電話を切ってしまったり、電話を内線転送しようとして操作を誤って電話を切ってしまうことがあります。
わざとではなくとも、待たされた上に電話を切られたということに不快感を抱く人も多いでしょう。
特に、電話をかけても回線が混みあっていてなかなか電話が繋がらないような場合や、急ぎの案件の場合、もう一度電話をし直す労力や時間を考えると、わざとではなくともクレームをいれたくなるものです。
万が一、電話を切ってしまった場合、もし相手の電話番号がわかるようであればすぐにこちらから電話をかけて謝罪することが大切です。
また、相手の電話番号が不明なときは社内で情報を共有しておき、相手から改めて電話があった際にすぐに謝罪が出来るようにしておきましょう。
保留後の対応が不適切
保留解除後に、そのまま質問の回答を伝えるようなことはしていませんか。
保留で待たされているところに、保留解除後にお詫びの一言もない場合、電話相手は「自分は蔑ろにされている」と感じるでしょう。そしてそのイライラや落胆は怒りに繋がります。
保留中は必ず相手を待たせているということを念頭に置き、保留解除後には必ずお詫びの一言をつけてから用件を伝えるようにしましょう。
また、保留解除後にすぐに用件を伝えずに、「えーっと」や「なんだったかな…」など、話が整理できていない場合も、電話相手のイライラや不快感を募らせる原因になります。
保留を繰り返す
繰り返される保留は、何度も待たされることから電話相手のイライラを増幅させます。
例えば、Aの質問を受けて保留してから回答すると、さらにその回答についてBの質問をうけたので保留して回答する…ということがあります。
ただし、これもあまりに何度も続くようであれば、詳しい担当者に電話を代わるか、折り返しの電話を提案する方がスムーズです。
折り返しの電話を提案する場合は、また何度も保留してしまわないように、質問されている商品やサービス、用件についてしっかり調べた上で電話をかけるようにすると良いでしょう。
電話対応中に保留にするときのポイント
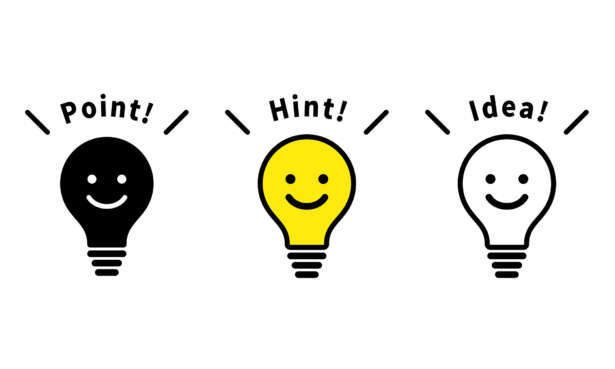
保留対応でクレームになるケースをご紹介しました。
この話を踏まえたうえで、電話対応中に保留を行う時のポイントをご説明します。
具体的には4つのポイントがあります。
・保留の理由を明確に伝える
・具体的な保留時間を案内する
・相手の了承を得る
・保留後は迅速かつ丁寧に再対応する
保留の理由を明確に伝える
今からどのような理由で保留を行うのかを明確に電話相手に伝えることで、少しでも電話相手を安心させる効果があります。
「少々お待ちください」だけ伝えられて保留をされるよりも、長く保留時間を待つことができます。
保留をする前に、下記の具体例のように理由を伝えると良いでしょう。
(例)
「確認いたしますので、少々お待ちくださいませ」
「お調べいたしますので、少々お待ちいただけますか」
「○○に電話をお繋ぎますので、少々お待ちください」
具体的な保留時間を案内する
調べ物や確認にかかる時間を予想できる場合は、具体的な保留時間を案内すると良いでしょう。
具体的な時間を聞くことで、電話相手は保留中に安心して待つことができます。
ただし、提示した保留時間は超えないように注意が必要です。
また、保留時間が長くなりそうな場合は、折り返しの電話を提案することも大切です。
具体例として、下記のような案内ができます。
(例)
「お調べするのに3分ほどお時間をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」
「確認いたしますので、申し訳ありませんが5分ほどお待ちくださいませ」
相手の了承を得る
了承を得てから保留対応を行うことで、電話相手もある程度の納得感をもって保留時間を待つことができます。
例えば「通話料が発生するから」や、「この後に用事がある」等の理由で保留の了承が得られない場合は、折り返しの電話を提案すると良いでしょう。
具体例として、下記のような確認の仕方があります。
(例)
「お調べするのに3分ほどお時間をいただきたいのですが、いったん保留させていただいてもよろしいでしょうか」
「確認いたしますので、一度保留させていただいてもよろしいでしょうか」
保留後は迅速かつ丁寧に再対応する
保留解除後は、電話相手を待たせていたということに対してお詫びの気持ちを表現する必要があります。
また、保留をしていない電話対応中であっても、相手の時間を使っているということを念頭に、迅速かつ丁寧に用件を伝える必要があります。
そのためには、保留解除前にどのように話し出すかをある程度決めておくことも重要です。
具体例として、下記のような対応があります。
(例)
「お待たせいたしました。ご質問いただいていたAの件ですが…」
「大変お待たせして申し訳ありません。先ほどお伺いした件で確認を取りましたところ‥‥」
電話代行なら「CUBEの電話代行サービス」
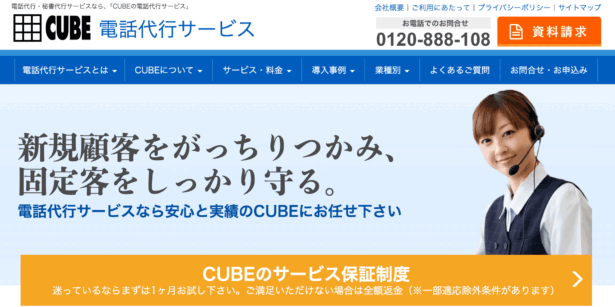
保留対応のマナー等についてご紹介してきましたが、理解は出来ても実践するとなると難しいのが電話対応です。
特に自社のスタッフに電話対応について教えるとなると、時間も人でも労力もかかります。
そんな時は、代表電話を代わりに受けて対応してくれる「電話代行サービス」を利用してみることをおすすめします。
特にCUBE電話代行サービスは、応対品質の高さに自信があります。電話対応について6か月間の教育や研修を受けた正社員のオペレーターが、貴社の代表電話の電話対応をいたします。保留対応のマナーはもちろん習得しているので安心してください。
多種多様な企業の皆さまに満足してご利用していただくために、電話代行サービスによくある外出応対だけでなく、内線感覚で電話をスマホに転送する「応答後転送サービス」や、クレーム一次対応、注文受付業務、予約受付業務、英語対応まで行っています。
少しでも気になった方は、是非お気軽にお問い合わせください。
ご相談のみも大歓迎です。
WEBでのお問い合わせはこちらから
オンライン個別相談の予約はこちらから
お電話のお問い合わせは
0120-888-108
まとめ
電話対応の一部である保留対応は、簡単なようでクレームを招きやすい対応の1つです。苦手意識がある方や、不安がある方がクレームを受けてしまえば、もっと電話対応が嫌になってしまうでしょう。
しかしそれでは、顧客や取引先とのコミュニケーションツールである電話対応がうまくいかないままになってしまい、自社にとってもマイナスです。
こんなときには電話対応を外注してしまうことで、流れを変えることができます。
CUBE電話代行サービスのオペレーターは、秘書検定と電話応対技能検定の資格を取得しており、電話での言葉遣いや心遣い、応対品質、臨機応変な対応には自信があります。
受電に関してはCUBE電話代行サービスに任せてしまうことで、顧客や取引先に好印象を与えながらスムーズなコミュニケーションが図れます。
電話対応に使っていた時間で、自社の電話対応の教育を行うことも可能です。
どんなサービスなのか?どんなことができるのか?ご興味がある方は、お気軽にご連絡ください。
WEBでのお問い合わせはこちらから
オンライン個別相談の予約はこちらから
お電話のお問い合わせは
0120-888-108