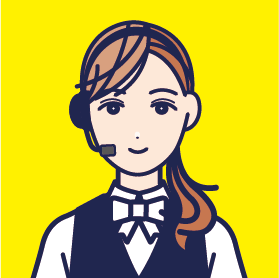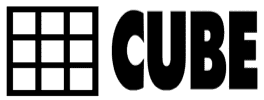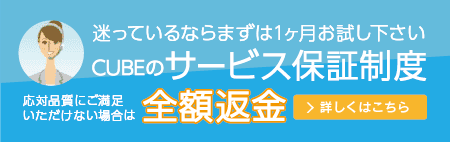【目次】
疲れにもそれぞれのタイプ
年齢を重ねるに従って、「疲れたな」と感じることが多くなってくる。私のサラリーマン時代を振り返ると、若い時には仕事帰りに仲間と居酒屋に行って憂さを晴らすようなこともしたが、何時の頃からかそれまで感じることのなかった体の重さのようなものが、一日の終わりにはずっしりと私の上に覆いかぶさるように感じたものだった。そんな有様だから仕事帰りにどこかへ寄り道するなんてとんでもない。ただ自宅と職場との間の往復だけで、仕事帰りは電車のつり革にぶら下がるように掴まって、家に帰るとそのまま崩れるような状態の毎日だった。
それでも私の場合、幸い大きな病気につながることはなかったが、読者の中にはそうでない方もおられるだろう。「疲れとは病気の手前で、体が発するSOSアラーム、つまり『体の声』です」と警告を発するのは免疫学の世界的な権威で、新潟大学名誉教授の安保徹氏。同氏は疲れと上手に付き合い、コントロールすることができれば、病気にはならず、それどころか体が本来持っているパワーを存分に発揮することができると、その著書「疲れない体をつくる免疫学」の中で話されている。その同氏が教えてくれるのは、疲れの中にもいくつかの「タイプ」があるということだ。
交感神経と副交感神経の関係
安保氏はもともと人間に備わっている免疫力によって病気を癒すことを専門にする免疫学の立場から、疲れのタイプやそのレベル、そして解消法を説明している。これによると、同じ疲れた状態であっても、自律神経の中で交感神経が優位になったことによる疲れを感じやすい人と、同じ自律神経の副交感神経の優位による疲れを感じることが多い人と分かれるそうだ。忙しすぎていつも疲れているようなビジネスマンは前者のタイプで、後者は例えば過保護に育てられた小学生が体を動かし始めるとすぐに疲れるような状態だという。大人でも女性を中心に3割ほどがこのタイプに相当する。
前者と後者では疲れの感覚は似ていてもそこに至るメカニズム、なりやすい病気がまったく異なるのだという。詳しくは著書に譲るが、主に昼間に働き人の元気な活動に関わる交感神経と、夕方から夜にかけて働き人にリラックスした状態を与える副交感神経は、通常は「シーソーのように」交互に活性化して体に働きかける。しかし、そのシーソーの働きを無視して働きすぎたり、リラックスしすぎたりした生活を続けていると、どちらか一方の神経だけが優位になり、もう一方の神経タイプに戻りにくい体質になると、偏った側に特有の疲れが現れ、その先に病気が待っていることになるのだそうだ。

イライラは交感神経、やる気が起きないのは副交感神経
いつも体が疲れている、イライラする、ピリピリした不安感が強い、原因を周囲のせいにして怒りやすい、興奮して夜眠れない、こんな疲れの症状があるのは交感神経が優位なタイプ。「交感神経が強いと元気はつらつで良いじゃないか」と思われても、この状態のまま休息が不十分な生活を続けると、先のような感覚が生じることになる。しかも、体は無意識にうまみの強いものや甘いものを欲するようになっていくのだそうだ。
逆に、人間はリラックスしすぎても疲れが出てしまうのだという。食事や入浴、睡眠など、副交感神経が優位になる時間を長く取り、交感神経を刺激する時間が少ない生活を続けていると、気持ちが沈んで、しょんぼりしやすくなっていく。そして、自然に交感神経への刺激を欲して、塩辛いものや冷たいものなど、刺激の強いものを食べたがる傾向を持つようになるのだという。このタイプの疲れの感覚としては、少し動くだけでも疲れる、やる気が起こらない、他人の目が気になる、小さなことが気になる、落ち込みやすい、などだ。
疲れから病気になる前に
交感神経が優位なタイプの疲れには、それが軽い間は手を止めて深呼吸を繰り返したり、少しだけ甘いものを摂ったりすることで随分状態は改善される。しかし、それが過ぎると深呼吸に加えて凝りや重さを感じる部位を動かす体操を10~20分すると良いそうだ。それが全身クタクタといった状態にまでなっていると、体の外から熱を与えることが必要になる。お腹や太もも、お尻、二の腕など、大きな筋肉が集まる箇所を湯たんぽやカイロで温めたり、ゆったりと入浴すると効果的なのだという。
一方、副交感神経が優位なタイプの疲れは、少し動いたくらいではダメで、数週間かけて生活のリズムを取り戻すことが必要のようだ。安保氏はまず日光をよく浴びることから始めることを推奨している。遅くとも午前0時には寝て、日の出とともに起き、そして日中は活発に活動をするような、交感神経を刺激する生活を心がけることが大切なのだという。気分が落ち込むだけでなく、活動量が少ないことからやせ細る、あるいは肥満傾向が出てきたりもする。
いずれにしても疲れが疲れのうちに留まっている間はまだ良いが、早めに手を打たなければ重い病気にまで発展しかねない。体からの予兆を「大したことはない」と軽く受け流していないで、自分の体が今どういう状況にあるのかしっかり認識しておかねば、いざという時に臍を噛む思いをしなければならなくなる。