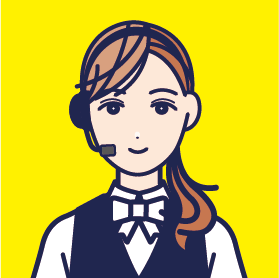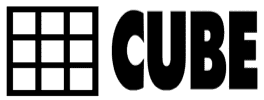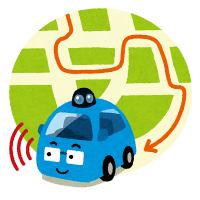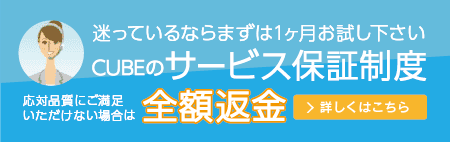【目次】
米国でポジティブ評価に転換
かつて米国の大手企業には厳格な人事評価制度があり、多くの会社がそれをお手本にしていた時期があった。
1980年代に導入されたのは、年に一度の勤務評定による各部署の社員の業績をすべて数値化し、下位の10%を解雇するというものだったという。
その年の評価では解雇されなくても、翌年に残った中の下位10%に属していれば解雇の対象になるかもしれないという厳しいものだったそうだ。
しかし、このところは社員の働きぶりのポジティブな面をより重視する傾向が強まっていると言われる。とげとげしいやり方は、実は益より害を多くもたらしかねないことに、多くのエグゼブティブが気づき始めているのだ。
ネガティブ評価がまだまだ幅を利かせる日本
そのようなことは当たり前と思えるかもしれないが、日本でも、より成果を上げることではなく、ミスをしないことを重視している傾向を残している会社はまだまだ多いように感じる。
「パワハラ」なる言葉がなくならないように、仕事の成果を評価する際に、ポジティブな面に重きを置くのは理想主義的すぎる、あるいは偽善的でさえあるという人たちもいる。
かつて、評価の過程でミスや過失を中心に議論するのが標準的だった時代に功績を上げ、管理職にたどり着いた者ほど、そうした見方にくみしやすい。誰しも自分の過去の栄光を自分で否定するようなことはしないのと同じだ。ポジティブ評価よりネガティブ評価がまだまだ幅を利かせているのだ。

社員個々に合わせた評価の仕方が大切
問題は悪いところを探し出すようなやり方によって、自信を失ってしまう社員が必ずいることだ。良い悪いではなく、彼らはきつく叱られることに動揺してしまい、挙句の果てに仕事に悪影響を及ぼしている。
人によってはそのストレスに耐えきれないと感じて辞めてしまうこともある。それを知りながら変わることのできない上司こそ、ネガティブな勤務評定を受けるべきなのかもしれない。

しかし、個々の社員次第ということもまた多々ある。中には歯に衣着せずに率直に自分の欠点を指摘してもらう方を好む人もいる。だから、一様にポジティブ評価に変えることが大切なのではなく、ネガティブ評価を受け入れられない社員がいることを認め、評価者が社員個々に合わせた評価の仕方をすることが求められているというべきなのだろう。
建設的な批判という方法も
あるいはひょっとしたら、ポジティブ評価とネガティブ評価の中間を行くやり方があるかもしれない。それは「建設的な批判」ともいうべきものだ。
例えば、「とても良い仕事をしているね」という口当たりの良い言葉だけを投げかけるのでなく、「もっと良い仕事ができるようになるためにはどうすれば良いか」ということを話し合うのだ。
「最良の教師は自分の失敗である」と言われるように、人は皆、仕事上で犯した失敗をくよくよするのでなく、自分の失敗から学んでいくという姿勢が求められる。評価する方もされる方も、価値観が変わった時代にいることを意識し、それに合った対応を心がけることが求められている。