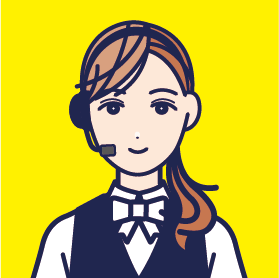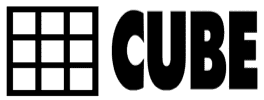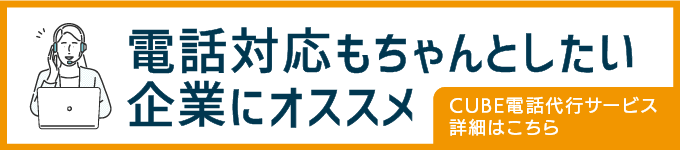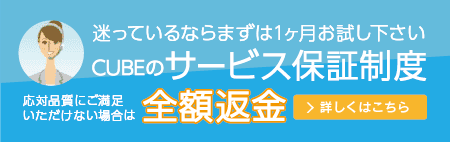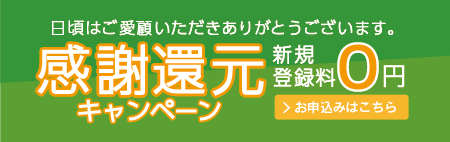電話対応は、IT化が進んでいる現代においても、未だ切っても切り離せない大切な業務のひとつです。
しかし、現代ではスマートフォンの普及により、固定電話をもたない家庭が増えたため、若手社員の中には「会社の電話に出るのが怖い」という声があるのも、また事実です。さらに、電話対応に対して恐怖心を持つ社員は、今後どんどん増え続けるでしょう。これからの若手社員たちが、電話対応に怯えずに、むしろ「電話対応が得意です!」と言えるようになるには、どうすればいいのか。具体的なマニュアルの作成方法を交えながらお伝えします。
【目次】
電話対応の基本
電話対応は、ビジネスを成功させるために欠かせないコミュニケーションツールの1つです。対応次第で会社の印象が左右されるため、電話対応の基本を理解し、マナーをしっかりと守りましょう。
基本1│ペンとメモ
電話の近くにペンとメモを用意しましょう。先輩や上司は、メモやペンを持っていないかもしれないですが、用意してください。「出来ないな。」とは、思われません。逆に、「おっ、最近の子にしては珍しい。良く出来るな。」と思う人が多いです。もし、「メモとペンなんて要らないだろう。」という人がいたとしても、そういう人は、伝言を間違えた方が怒ります。ペンとメモを用意してください。もし、出来るならメモには
① 会社名
② 部署名(必要なら)
③ お名前
④ 宛先
⑤ ご用件
⑥ 電話番号
⑦ 折り返しの電話の 要 ・ 不要
⑧ 会社・部署ごとに必要な項目
これだけ印刷していると安心です。②と⑧は、自社に合わせてカスタマイズしてください。メモの紙が無駄と思う場合は、PCのメモ帳を使ってタイピングしても良いです。電話のヒアリングや応対に集中できる方を選んでください。
基本2│電話機の基本操作を覚える
上司や先輩は、固定電話を家で頻繁に使っていた人が多いです。自宅電話でキャッチホンや、子機があり保留から転送、元に戻すなど普通に会社に入る前に使っていた人も多いです。その為、当たり前すぎて教えてくれない人もいます。今は、固定電話の操作方法をそこまで知っている方が普通ではないですから、安心して教えてもらいましょう。ビジネスフォン(固定電話)の基本の使い方を覚えておきましょう。
① 保留
② 保留から元に戻して対応
③ 保留してから、他の固定電話へ内線をかける方法
④ ③で話した後に転送する方法
⑤ ③で話した後に元に戻して、自分が話す方法
⑥ その他
基本的には、上記を覚えれば大丈夫です。上記以外は、特殊なので多くの場合は先輩社員が教えてくれます。ビジネスフォンの場合、メーカーや設定で操作が異なるので、前職と同じメーカーでも確認してください。
基本3│まず自分から名乗る
スマートフォンや自宅電話は、「もしもし、」と応対し、先方から名乗ってもらうのが基本です。プライバシーやセキュリティを守るためですね。でも、会社の電話は、公の電話ですから、「ありがとうございます。〇〇会社でございます。」と先に自分から名乗りましょう。AM10時まであれば、「おはようございます。〇〇会社でございます。」と時間によって対応を変える会社もあります。
基本4│敬語や敬称の理解
自分の会社⇒弊社、相手の会社⇒御社、上司も呼び捨て呼ぶ、わかりました⇒承知しました等、ビジネスで使う敬語、謙譲語、尊敬語等、覚えましょう。電話対応だけでなく、顧客対応全般や社内でも、コミュニケーションがスムーズになります。満点でなくても大丈夫です。先輩や上司も、何度も使ってスキルアップしていますし、完璧に使いこなせる人もほとんどいません。それでも、十分レベルの高い対応は出来きます。まずは、一つ一つ覚えましょう。
基本5│事業内容、部署の業務、各担当の理解
会社の代表電話には、様々な問合せがあります。既存顧客、新規顧客、取引先、銀行、営業電話、間違い電話。教えてもらえる先輩が居たら、どんな問合せがあって、その場合は誰に取り次ぐのか、不在の場合は、何をお伺いすれば良いのかを確認しましょう。教えてもらえる人がいなければ、事業内容や、組織体制(部署)、各担当を時間があるときに把握しましょう。慣れるまで、応対中困った時は、顧客、取引先として対応すると安全です。営業の電話を顧客や取引先と間違えても、怒られるかもしれませんが大事にはなりません。顧客や取引先を営業として扱うと怒られるだけではなく、会社に損害を与えるかもしれません。

電話を受ける時のポイント
電話は、お互いの顔が見えないツールです。そのため、会社の印象は電話対応をする社員の声や言葉使いの印象に左右されることになります。
特に、若手社員に電話対応を任せる際には、自分が“会社の代表者である”という自覚を持って、好印象の電話対応を心がけてもらうことが大切です。好印象の電話対応をするには、話し方にポイントがあります。
新入社員の電話対応マニュアルの基本!コツや注意点について
※飲食店店長へオススメ!飲食店の電話対応マニュアル新人向け
※例文で学ぶ電話対応~電話対応のマニュアル&テンプレート集~初級~中級
①電話対応をするときには正しい姿勢で
電話機はデスク上に置かれている場合が大半ですから、電話を受ける際にはやや前かがみの体勢になってしまいます。さらに、手元の資料を見ながらや、メモをとりながらだと余計に下を向く姿勢になってしまいます。
電話をする際に、下を向いた姿勢であったり、足を組んだりしていると、姿勢がゆがむため、発声も悪く・声のトーンも低くなり、暗い印象をもたれてしまいます。
そして何より、相手にこちらの姿は見えないと油断してしまいがちですが、実は電話対応中の態度や姿勢は、思っているよりも声の印象にのって相手に伝わってしまうものです。足を組んだ状態だと気持ち的にもだらけてしまうので、相手にもその印象が伝わってしまいます。
多くのマニュアル本に、謝罪の電話の際には、相手が前にいるのと同じように、実際に頭を下げましょうと書かれているのも、こういった要因にあります。
電話対応をする際には、目の前にお客様がいらっしゃるときと同じように、姿勢を正しましょう。
②口角を上げて笑顔で対応する
電話対応では、お互いの顔が見えないので笑顔など不要だと思われる方が多いですが、口角が下がった状態で話をすると、声のトーンが下がってしまいます。
口角を上げると声のトーンも明るくなり、また、口が大きく開くので、自然と聞き取りやすい発声になるのです。電話機を通すと、声がこもり聞き取りにくい状態になってしまうので、明るく聞き取りやすいように話すのがポイントです。
また、①の姿勢の際と同じように、こちらの表情は声の印象として相手に思っているよりも詳細に伝わってしまいます。通常の電話対応の際には笑顔で、クレームなどの電話対応の際には逆に真剣な表情で、その場にふさわしい表情で対応することが大切です。
③他の作業は一旦止めて、電話とメモに集中する
電話対応中にほかの作業をしていると、相手の名前やご用件がうまく聞き取れなかったり、忘れてしまったりすることが起こります。一度言ったことを、何度も聞き直されたり、理解していなかったり、さらには名前を間違えられたりすれば、誰しも気分はよくないでしょう。電話に集中して一度聞き取ったことは必ず忘れないようにメモを取る習慣をつけましょう。
また、忙しいからといって、焦っている中で電話対応をしてしまうと、早口で聞き取りづらくなってしまいますから、電話対応をする際には、必ず他の業務の手をとめて、一度心を落ち着けてから対応するとよいでしょう。
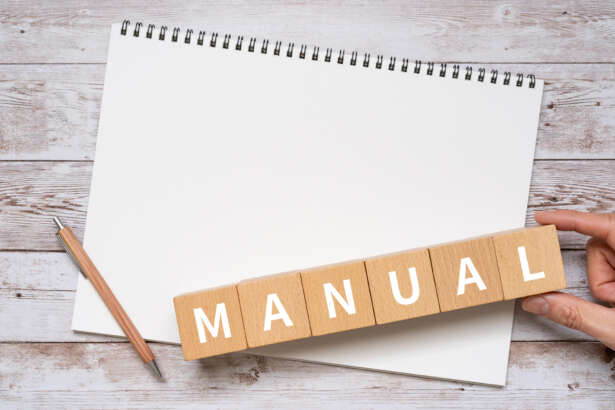
電話を受けたときのマナー
ビジネスの電話対応には、最初に名乗って挨拶をする、その後お相手の社名とお名前と簡単な用件の概要を聞くといった、決まった流れが存在しています。その流れを理解しておくことが、電話対応をスムーズに行うにあたって、とても大切なことです。
①2コール以内に電話を取る
電話をかけてこられたお相手をお待たせしないように、目安として2コール以内に受話器を取るようにしましょう。稀に、電話対応が苦手な社員であれば、ほかの人が電話をとってくれないかという期待から、少し待ってしまうといったこともあるようですが、急ぎの用件やクレームのお電話の場合は特に、そうでなくてもお待たせすることで、相手が気分を害されてしまい、それが結果クレームや電話対応が長引く、難しくなるといったことにもつながりかねないので、電話が鳴っていることに気づいたら、なるべく早く電話を取るようにしましょう。どうしても忙しく、3コール以上お待たせしてしまった場合には、「お待たせいたしました。」と声をかけるようにしましょう。
②自社名を名乗って、挨拶する:「お電話ありがとうございます。株式会社○○です。」
電話対応において印象の良し悪しは、よほどその後の対応においてアクシデントが起こらなければ、最初の第一声で決まります。特に、電話に出て最初にご挨拶をするときには、丁寧で明るい印象になるように、発声や話すスピードには気をつけましょう。もくもくと作業を行っている中では、声が出辛くなっていることもあるので、余裕があれば、一度受話器を取る前に、挨拶の練習をしてみるのもおすすめです。
③お相手の社名・氏名を伺い、復唱確認する
電話対応で特に重要な情報の一つが、【誰から】かかってきた電話であるかということです。相手の社名や氏名をきちんと聞き取れないまま、担当者に繋いでしまったり、折り返しの提案をしてしまったりすると、担当者が違う相手からの電話だと勘違いしてしまい、話がかみ合わない、相手のお名前を間違えてしまい失礼な対応になってしまったり、折り返し先の電話番号を聞き忘れた、聞き間違えたという場合に折り返しのご連絡ができなくなるといったトラブルが起こることも考えられます。
こういったトラブルを回避するためにも、必ず社名、氏名は復唱して確認をとるようにしましょう。名前を仰らずに用件を話し始めた、聞き取れなかったという場合には、
「恐れ入りますが、御社名とお名前をお伺いしてよろしいでしょうか。」
「念のため、もう一度御社名(お名前)をお伺いしてもよろしいでしょうか。」
と言って、必ず正確に聞き取るようにしましょう。
④簡単なご用件の概要を伺う
電話対応において重要な要素のもう一つがご用件です。担当者を名指しの場合であっても、電話を内線で回す、もしくは伝言メモを渡す際に用件は必要です。用件によって、緊急なのかどうなのかが変わりますし、用件が分かったほうが担当者も業務の優先順位をつけやすくなります。また、担当者にまわす必要のない営業電話をまわしてしまって社内の業務効率を下げないためにも、ご用件を伺うことは大切です。用件を仰らない場合には、「差し支えなければ、ご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか。」と確認しましょう。
⑤担当者が自分以外なら、担当者が在席しているかを確認して電話を回す
お電話の用件が、自分で対応できない範囲であった場合や、ほかの担当者を名指しであった場合は、「担当の者に確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか。」と相手に確認して保留ボタンを押し、対応部署または担当者が在席しているか、今電話対応をできる状況かを確認しましょう。
⑥担当者不在なら折り返しの提案をする
お電話の用件に対して答えられる人や名指しの担当者が、外出中や来客対応中で今すぐに電話対応ができないという場合には、保留を解除し「○○様、お待たせして申し訳ございません。恐れ入りますが、担当の××は只今外出中でございます。よろしければ、××から折り返しお電話差し上げましょうか。」とすぐに対応できない理由を述べ、謝罪し折り返しの提案をしましょう。
⑦折り返し先の電話番号を伺い、復唱確認する
折り返しのお電話に了承をいただけた場合は、担当者の戻り時間がわかっていれば「担当の××が15時に戻り予定ですので、それ以降の折り返しとなりますがよろしいでしょうか。」とお伝えし、「ご都合の悪い時間はございますか。」とお相手の電話対応可能時間を聞き取りましょう。その後、「折り返し先のお電話番号をお伺いできますでしょうか。」と確認し、かからないといったことがないように必ず「復唱いたします。お電話番号が03-1234-5678、内線番号が123でございますね。」と復唱して確認しましょう。
折り返しは不要で伝言のみお願いしますと言われた場合は、ご伝言の内容を復唱確認しましょう。
⑧終わりの挨拶をする
電話対応にて聞き取らないといけない内容に聞き漏れがないかどうか、自分の中で再度確認がとれたら、
「それでは、担当の××より本日15時以降に16時~17時の時間を避けて、お電話差し上げます。失礼いたします。」
「私から担当の××に【ご伝言内容】の旨、申し伝えます。失礼いたします。」
折り返しや伝言は結構です。こちらからまた改めます。と仰られた場合には、「○○様からお電話があった旨、担当の××に申し伝えます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。」と締めくくると良いでしょう。
⑨相手が電話を切ったのを確認してから受話器を置く
電話対応では、電話をかけた方が先に電話を切るのがマナーです。必ず、相手が受話器を置いたことを確認してから、電話を切りましょう。

電話対応が難しい場合の対応方法
電話対応の基本の流れを理解していても、緊急のご用件やクレームのお電話の場合など、臨機応変な対応が求められるのが、ビジネスにおける電話対応です。
基本の電話対応は問題なくこなせていても、突然の予期せぬ内容の電話に応用した対応ができず、その結果、電話対応に苦手意識をもってしまう若手社員も少なくはありません。
電話対応はお客様それぞれによって、必要な対応が変わってくるので、電話対応を完全に網羅したマニュアルは存在していません。しかし、クレームのお電話の際にしてはいけないポイントや、こう言ったほうが良いという言い回しはある程度存在しています。こういったことをマニュアルではポイントとして抑えることで、突然の電話対応にも慌てることなく対応することができます。
緊急のご用件の電話対応
緊急のご用件の電話の場合は、相手はお急ぎになっておられる場合が多いです。素早くご用件をお伺いし、対応することが大切です。担当者不在ですぐに対応ができない場合には、その旨をお伝えし、長らく保留でお待たせさせずに、担当者が不在の理由と、担当者の予定がわかっていれば、その予定が終わり次第すぐに折り返すようにいたしますとお伝えしましょう。
緊急の用件の場合は、可能であれば担当者の携帯電話に直接電話をし、すぐにご伝言を伝えましょう。移動中や打ち合わせ中ですぐに電話がつながらない場合には、留守番電話に録音する、または担当者の携帯電話のメールやチャットツールなど、なるべくすぐに担当者が伝言を確認できるツールに【至急対応】とわかるように、伝言を残しましょう。
クレームの電話対応
クレームの電話の場合には、笑顔での対応ではなく、真摯な表情で電話対応することが大切です。謝罪をする際には、相手にこちらの姿は見えずとも、実際に頭を下げるとよいでしょう。こちらの表情や態度や声を通して相手に必ず伝わるものだからです。
また、緊急のご用件の際と同じように、相手をお待たせして二次クレームにつながらないように、素早い対応がクレーム対応には求められます。ご用件をお伺いし、なるべくお相手をお待たせしたり、たらいまわしにしたりしないようにしましょう。すぐに対応できない場合は、その旨をお伝えし、折り返し先とご都合の良い時間を伺い、折り返しの約束をするとよいでしょう。
相手が名乗らない場合
電話をかけてきた相手が付き合いの長い取引先であった場合や過去に在籍していた役職者である場合、または上役の親族などの場合には、自分のことを知っているという前提で名乗らないケースもあります。そのような場合には「恐れ入りますが~」「失礼ですが~」「差し支えなければ~」といったクッション言葉を添えて、「お名前をお伺いできますでしょうか。」と失礼のないようにお伺いしましょう。
相手がお急ぎの様子で、どうしてもお名前を名乗ってもらえない場合には、担当者にそのまま伝えて、電話を取り次いでもらいましょう。担当者が不在の場合は、担当者が所属している部署やチームの方に尋ねれば、その人のことを知っている/担当者の代わりに対応できる人がいるかもしれません。相手の様子に合わせて臨機応変な対応をすることが好印象の電話対応には大切です。ご用件を言ってもらえない場合も同様です。
相手の声が聞こえない時の電話対応
電話の相手が駅のホームなどから電話されていて、周囲の雑音が多く声が聞き取りにくい場合や、声が小さくて聞き取りにくい場合、電波状況が悪く声が途切れ途切れになってしまう場合には、
「恐れ入りますが、お電話が少々遠いようでございます。」
「申し訳ございません。電波が悪く、聞き取ることができませんでした。もう一度お願いいたします。」などとお伝えしましょう。
電波や電話機の不具合で全く相手の声が聞こえないという場合には、何度か「お電話聞こえておりますでしょうか?」と呼びかけ、それでも何も返答がない場合には、「申し訳ございませんが、お電話聞こえませんので失礼させていただきます。」と切電するとよいでしょう。

電話をかけるときのマナー
IT化により「電話をかける/受ける」頻度がかなり減っている現代社会ではありますが、仕事をする上では欠かせない電話対応。いざ電話をかける/受ける時に慌てないために押さえておきたい【電話対応の基本・ポイント】をご紹介します。
事前に用件をまとめる
伝えたいことがあるから、電話をかけるのですが、気持ちが先走って電話をかける方がいます。また、整理されていないと話の途中で相手から話の腰を折られたり、別件の話をされて、自分が伝えたかったこと、確認したかったことが聞けないまま、相手が電話を切ってしまうこともあります。相手に合わせて短時間で終話できるように、慣れるまでは用件をまとめておきましょう。
時間帯に注意する
相手にとって都合が悪い時間帯、例えば、始業間際、お昼、終業間際、スケジュールを把握している場合は、その時間帯は避けましょう。但し、相手にとって重要・緊急時には、勇気を持って電話しましょう。
その際は、例えば、お昼時であれば、自分の社名、名前を伝えた後すぐに、「お昼時に申し訳ございません。〇〇の件で急ぎでお伝えしたいことがあるのですが、今よろしいでしょうか。」等と、何の件か、緊急であることがわかるように確認しましょう。
相手の都合の悪い時間帯に、緊急時、トラブル時で電話をするときこそ、スムーズに伝えなければいけません。そういう時こそ事前に用件をまとめましょう。
聞取りやすいようにハッキリ話す
最近は、マスクをしながら話すことも多いかもしれません。意識して口を大きく開けてハッキリ話しましょう。電話だと声が籠るので、オーバーリアクションでも良いぐらいです。恥ずかしがらずに、相手の方が聞き取りやすいように話しましょう。特に携帯電話、スマートフォンの場合は、電波状況も気をつけて、固定電話よりもはっきりと話しましょう。最近ではクラウドPBXを利用している企業も増えています。クラウドPBXの種類によっては、通常の電話回線よりも音質が劣化しているケースがあります。普段から劣化している場合は、気をつけて話すでしょうが、時間帯やタイミングにより劣化するケースも少なくありません。相手の反応に合わせて口や声の大きさは調整しましょう。
取り次ぎをお願いする
一般的なケースでは、担当者〇〇さん宛にお電話をかけます。
「お世話になっております。株式会社〇〇(会社名)□□(△△(自分の名前)です。■■(相手企業の規模により部署名)××様いらっしゃいますでしょうか。」普段から、取引がある方へのお電話では、手短に取次をお願いした方が、取り次ぐ方が時間を取られずに済みますので、相手の名前を伝えて取り次いでもらいましょう。
しかし、取引が初期の段階や、電話でのやりとり頻度が低い方へのお電話の場合、営業電話と誤解される場合もあります。電話を受けた反応が「誤解されているかな?」と思った際には、簡単に用件を伝えましょう。「先日、××様からご依頼いただいた~~~~の件でお電話させて頂きました。」等、端的に用件を伝えましょう。注意が必要なのは、社内へ内密な案件で社長や管理職の方とやり取りしている場合は、当然用件を伝えることは厳禁です。「今××様にご依頼頂いている件でお電話させて頂きました。」等の言い回しで取り次いでもらいましょう。
担当者が在席している場合
担当者が、在席で取り次いでもらった場合、再度挨拶と社名等を名乗ってから用件をお伝えしましょう。タイトル+詳細という感じでお伝えするのが望ましいです。
「いつもお世話になっております。株式会社〇〇(会社名)(△△(自分の名前)です。先日ご依頼いただきましたお見積りの件(タイトル)でお電話させて頂きました。今、少しお時間よろしいでしょうか。それから用件をお伝えしましょう。
担当者が不在の場合
担当者が不在の場合は、用件と担当者のスケジュール、窓口の方の回答によって対応しましょう。
「15時まで会議の予定です。」や「外出しており、16時戻りの予定です。」と言われれば、急ぎでなければ、
「改めてお電話させて頂きます。失礼いたします。」「株式会社〇〇(会社名)(△△(自分の名前)から電話があった旨お伝え頂いて宜しいでしょうか。」「●●の件でお電話頂きたい旨お伝え頂いて宜しいでしょうか。」「〇〇の納期の件ですが、予定より早まり3日になる旨お伝え頂いてよろしいでしょうか。」と伝言をお願いしましょう。
急ぎの場合は、急ぎの旨と用件をお伝えしましょう。
「〇〇の件で△△になりまして、急ぎご連絡頂きたいのですが、お伝え頂けますでしょうか。」詳細伝えても良ければ、より具体的な用件をお伝えし、外出先や会議中でも確認を取るかどうかは、先方の応対者へ判断を委ねましょう。

電話対応で使えるフレーズ
電話対応が苦手な人も、もっと上手になりたいの人もこれを覚えておけば大丈夫!
実際にCUBEスタッフが使っている「一つ上」の対応フレーズをご紹介します。
【電話応答時】
「お電話ありがとうございます。株式会社○○(+自分の名前)でございます」
社名の後に名乗りを入れると、より丁寧さがアップします!
【取次時】
<担当者不在時、代わりに伝言や用件を聞く>
「もしよろしければ、私でご伝言をお預かりいたしましょうか。」
「あいにく○○は外出しておりますが戻りましたら、折返しお電話を差し上げるように申し伝えましょうか。」
クッション言葉を入れると、やわらかい印象になります!
<用件や名前が一部しか聞き取れなかったとき>
「申し訳ございません、お電話が少し遠いようです。もう一度どちらの○○様かお教えいただけますか。」
聞き取れた一部分だけでも復唱すると、相手に安心感を持ってもらえます!
<詰まった、噛んだ>
大丈夫!まず「一息」入れて、「失礼いたしました」と一言お詫びの上、対応を続けてみましょう。
暗い気持ちが声に出てしまいがちですが、それよりもハキハキと、丁寧に対応を続けると自然と持ち直します!
守るべきマナーが多い電話対応ですが、一つずつ身に着けていきましょう!
是非、明日からご活用くださいませ!
電話対応に関するよくある質問
電話対応に関する疑問や確認するポイントは、業種業界、会社規模、事業所規模によって多種多様にあります。その質問と回答をこの記事内で全てご紹介することは難しいため、「よくある質問」の中から2つに絞って解説していきます。
電話対応の基本マニュアルは?
電話対応のマナーやポイントを元にした基礎的なマニュアルを作りたいと思われる方や、とにかく基本的なマニュアルが欲しいと思われる方は多くいます。
基本のマニュアルを下記にまとめました。
①会社の代表として受電(架電)している意識を持つ
②最初に挨拶をする
③社名や部署名、自分の名前をはっきりと伝える
④相手の社名、名前、用件は復唱して確認する
⑤聞き取れなかったことはそのままにせず、もう一度確認する
⑥誰かに電話を取り次ぐときには保留にする
⑦相手が電話を切ってから静かに受話器を置く
この7点を、電話対応の基本マニュアルに入れると良いのではないでしょうか。
電話対応でダメな例は?
電話対応の悪い例やダメな例についても知りたい方はたくさんいます。良い電話対応は急には難しいけれど、せめてダメな電話対応は避けたいと思うからではないでしょうか。
電話対応でダメとされる例を下記にまとめました。
なかなか電話に出ない
他のことをしながら電話に出る
食べながら電話に出る
電話を長く保留にしたままにする
相手の話をさえぎる
声が小さい、早口
相づちを打たない
曖昧な回答しか言わない
「わかりかねます」や「いたしかねます」ばかり言う
クッション言葉を使わない
相手が話している途中で被せて発言する
このような例が挙げられます。
まとめ:柔軟に電話対応ができるようになるためには、マニュアル作りが大切!
お客様や取引先様からの電話対応方法には必ずしも正解がなく、電話をされてきたそれぞれに合わせて柔軟に、臨機応変に対応することが求められます。マニュアルに自社で考えられる様々なケースを想定して記載することで、正解に近い対応をとることは可能になりますが、それは簡単なものではありません。電話対応の豊富な経験と知識があってこそ、限りなく多くのお客様に好印象を持っていただける電話対応を行うことができるのです。
すぐにでも、電話対応で自社の印象をアップしたいという経営者様は電話対応サービスをおすすめいたします。
CUBE電話代行サービスなら、
・CUBEスタッフが自社スタッフとしてお電話を取ったあと、内線感覚で担当者の携帯電話などにお繋ぎする“応答後転送サービス”があるので、事務所にいる時間は直接お客様対応をしたい営業マンや、緊急時の素早い対応で信頼関係を築きたい経営者の方にもおすすめです!
・新規案件はAさんへ、求人の用件は人事担当のBさんへメール連絡、重要取引先からの電話は社長の携帯電話へ応答後転送など、“ご用件別振り分け”での報告が可能ですので、ほかの人の報告に埋もれて自分宛の報告を見逃してしまった!という対応漏れも防げます!
・普段お使いのMicrosoft TeamsやSlackなどのチャットツールで、受電報告を受信することも可能ですので、DMや迷惑メールが多くて、受電報告が埋もれてしまう心配もありません!※別途オプション
他にも、さまざまなオプションを取り揃えておりますので、自社にぴったりな電話対応をオーダーメイド感覚で組み合わせることができます。
気になった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
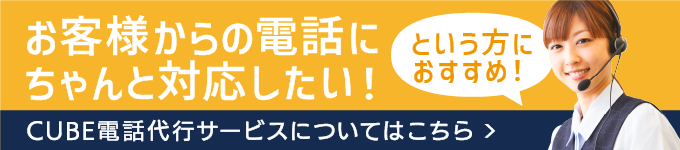
●CUBE電話代行サービスに関するご相談・お問い合わせ先
メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら
お見積り依頼はこちら
お電話でのご相談・お問い合わせは、直通ダイヤル 0120-888-108
平日(月~金):9:00~18:00 ※祝日と年末年始・GW・お盆はお休みをいただいております