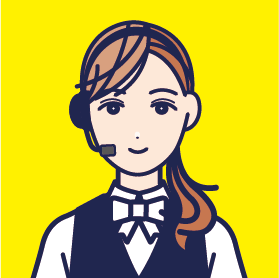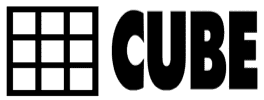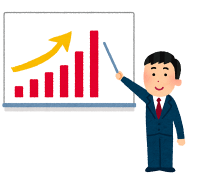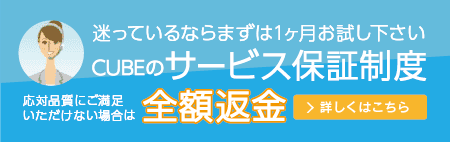【目次】
5日以上の有給義務化
働き方改革の一環として、年10日以上の年次有給休暇(有給)を付与されている労働者は、4月から5日以上の有給取得が義務づけられる。対象となるのは社員だけではない。契約社員やパート・アルバイトも含まれる。特に大手企業に比べて中小企業の有給取得率は低い水準に留まっているのが現状だが、それでもすでに有給消化を義務付けている企業も多くある。人手不足も重なって対応に苦慮する企業もあるものの、取得率の格差の広がりをそのままにしていては、これから将来の勤務先としてますます敬遠されるようになる。こうした「強制的」な処置を前向きにとらえて、自社にどう取り込むかが課題になっている。
実は有給の取得に関しては、ある程度の規模の中小企業においてはすでに対応済みのところも多くある。あるプラスチック加工メーカーでは有給の取得率向上に5年前から取り組んでいる。同社では1年を通して無遅刻・無欠勤だった社員に皆勤手当1万円を支給していたが、有給を取得すると従来はこの手当がつかなかったという。これが有給を取得しにくい要因の一つになっていると考え、2014年度からは皆勤と見なす有給を1日ずつ増やし、現在の年休の平均取得日数は5日を超えた。このメーカーでは振り返ってみて、「有給の取得率向上は経営者の伝え方次第」と言い切る。

中小企業でも対応が進む
別の金属加工メーカーでは2008年から年間5日の有給取得を義務化している。同社が指定した5日間は全社員が休日になる。その社長は「会社側が有給取得を促すことで休みを取りやすい環境を整備し、働きやすい職場作りに生かしたい」と狙いを語る。同じ年から同じく年間5日の「計画有給制度」(予め有給を使う日を年初に個人に申告させておく)を実施している産業用ヒーターを開発するベンチャー企業は、計画以外の有給も取得できている社員が多く、ここの社長は「さらに取得率を上げていきたい」と前向きだ。
このほかにも、「すでに年2、3日は強制的に有給を取得させており、残り2、3日についてもしっかり指導する」としているところなども多く、今回の年5日以上の義務付けに対しても余裕を持って対応しているところは少なくないようだ。中には、「すでに現状でも完全週休2日制で祝日も休みと大手企業並みの待遇を確保しており、将来は2日働いて1日休むようにできれば」とさらにその先を睨んだ働き方のイメージを膨らませている中小企業もある。
有給を取得する人、しない人
しかし、それなら問題がないのかと言えばそうでもない。よくよく勤務の中味を聞けば、業務が一部の社員に集中しており、残業や休日出勤で対応している状態などが明らかになっている。そうしたところでは、「残り2、3割の社員に有給をどうやってとってもらうかの方法を確立することが頭の痛い問題」だという。そうしたところでは、期初に年間計画を作り、順次休んでもらうなどの案が考えらえているところだ。別のベンチャー企業でも、「有給を取得する人としない人の両極端に分かれる。特に現場で主力となる人は休まない(休めない)傾向にある」としている。
こうなると、いかに休むように指示を出したところで無駄だ。言うなれば、そもそも組織の在り方が有給を取りにくくしているのだ。だから、ただ「休みなさい」と掛け声をかけるだけでなく、仕事の割り振りの見直しや、繁忙期と閑散期の平準化、さらに休日が増えても生産性を維持ないしは向上させるための工夫がなければ、一時的には有給取得率が高まっても長期的には成り立たないだろう。本来これら一連の対策と同時に考えなければならないが、それではなかなか進まないので、そのための第一歩を今回の義務化で取り組んでいくと捉えた方が良い。

どの程度現状をつかんでいますか
中小企業の有給休暇の取得に詳しいある社会保険労務士は、「そもそも中小企業の中で1人の社員に年次有給休暇をどれだけ付与し、かつ消化されているかを正確に把握している企業がどれだけあるのか気になるところだ」と懸念する。「通常は入社後の半年間で8割出勤すれば10日の有給休暇が与えられるのだが、中途入社の多い企業では、有給休暇の付与日(基準日)が社員によってバラバラになり、管理が煩雑になる」からだ。そこで、それを避けるために、「基準日を統一する」ことも検討してはどうかと提案をしている。
ここで紹介した声はいずれも有給休暇の取得に前向きに取り組んでいる企業ばかりだったが、そもそも義務化される5日の有給休暇すら取得させていない企業もまだまだあるに違いない。そうした現状の実態把握をまず自社内で急ぎ、取得が進まない原因を探るとともに、場合によっては年末年始や夏のお盆休みなど、業務の余裕があると思われる時期に計画的に有給休暇を取得させることも必要になるのだろう。まだまだ労使ともに関心が今一つ薄い状況にあるようだが、これによる今以上の格差拡大はこれから企業の存続の上でも致命的なものになりかねない。